「急性呼吸不全」について解説
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)

呼吸ができなくなると、全身の細胞への酸素の供給が止まり、脳や心臓がダメージを受けます。
急性呼吸不全は極めて予後が悪く、命の危険もあるため、すぐに酸素投与や人工呼吸器が必要になる場合があります。
この記事では急性呼吸不全の症状や原因、検査、治療について詳しく説明しています。
1.呼吸とは?

呼吸には外呼吸・内呼吸の2種類があり、細胞の代謝によって生じた二酸化炭素を排出し、細胞がエネルギー産生するのに必要な酸素を取り込むために行われます。
「外呼吸」は、口や鼻から空気を取り込み、肺の中にある「肺胞」と呼ばれる組織でガス交換を行うことを指します。
肺で酸素を受け取った血液は心臓に運ばれ、拍出されて全身の細胞に行き渡ります。細胞の二酸化炭素を回収し、酸素を供給することを「内呼吸」といいます。
もし呼吸が止まってしまうと、体に酸素が行き届かなくなり、脳や心臓がダメージを受けます。
特に脳は、酸素の供給が10秒止まると意識がなくなり、1分止まると呼吸停止、3~4分止まると後遺症が残る可能性が高く、10分以上になると脳機能の回復は望めないと言われています。
【参考情報】日本心臓財団『1秒でも早く』
https://www.jhf.or.jp/sousyo/image/Heartno10.pdf
正常な呼吸を行い、全身の臓器に酸素を届けるためには、次の5つの機能が欠かせません。
①呼吸中枢の働き
:呼吸は、脳の「延髄」という場所でコントロールされています。
延髄の呼吸中枢が、酸素不足や二酸化炭素の増加を感知し、自動的に呼吸を調整してくれる仕組みになっています。
例えば脳卒中や、事故による頭部外傷などによって呼吸中枢が損傷すると、自発呼吸ができなくなります。
②呼吸筋や胸郭の働き
:肺は、自分の力だけで膨らむ(=空気を取り込む)ことはできません。
横隔膜や肋間筋などの呼吸筋が伸び縮みすることで、肺の容積が変化して空気の出し入れが可能になります。
例えば筋ジストロフィーやALSなどによって横隔膜に麻痺が起こると、自力で息を吸うことができなくなります。
③気道の確保
:口や鼻から肺までの、空気の通り道が確保されている必要があります。
例えばアナフィラキシーショックで気道が閉塞すると、窒息の恐れもあります。
また、閉塞までいかないまでも、喘息などで気道が狭窄すると息苦しさを感じます。
④肺胞の働き
:肺胞がダメージを受けると、線維化して硬くなったり、弾力性を失ったりしてしまいます。
このように肺胞がしっかり膨らまない状態では、正常なガス交換は行われません。
間質性肺炎やCOPDなどが原因で肺胞が破壊されると、酸素を取り込みにくくなり、息苦しさを感じます。
一度破壊された肺胞は元に戻らないため、日常生活が難しいほどの息切れや、在宅酸素療法が必要になる場合もあります。
【参考情報】日本呼吸器学会『慢性閉塞性肺疾患(COPD)』
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/b/b-01.html
⑤血液の酸素運搬機能
:赤血球中の「ヘモグロビン」というたんぱく質が酸素を結合して、全身の細胞に運びます。
そのため、貧血の場合は酸素の運搬能力が低下し、息切れなどの症状が起きることがあります。
【参考情報】国立長寿医療研究センター『貧血の原因は?』
https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/11.html
このように、呼吸は多くの機能が適切に働くことによって成立しています。
2.呼吸不全とは?

呼吸不全とは、動脈血中の酸素分圧(PaO₂)が60mmHg以下の状態を指します。
似たような言葉で「呼吸困難感」というのを聞いたことがあるかもしれませんが、呼吸不全とは意味が異なります。
呼吸困難感は息苦しさを感じる主観的な症状なのに対して、呼吸不全は数値ではっきりと定義されています。
また、期間や状態によって次のように分類されます。
①期間による分類
・慢性呼吸不全:呼吸不全の状態が1か月以上続くもの
・急性呼吸不全:数時間~数日と短い期間で急に発症するもの
【参考情報】日本呼吸器学会『慢性呼吸不全』
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-02.html
②状態による分類
・Ⅰ型呼吸不全
・Ⅱ型呼吸不全
Ⅰ型呼吸不全は、肺のガス交換がうまくいかず、十分な酸素を取り込めないために低酸素血症(血中の酸素不足)が生じる状態です。
Ⅱ型呼吸不全は、酸素を取り込む力だけでなく、二酸化炭素を十分に排出する力も低下しているため、低酸素血症に加えて二酸化炭素が体内に蓄積してしまう状態です。
Ⅰ型・Ⅱ型の判断基準となる数値については3章で詳しく説明します。
【参考文献】”Respiratory Failure” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24835-respiratory-failure
3.急性呼吸不全の症状

急性呼吸不全は、数時間~数日ほどの急激なスピードで発症するのが特徴です。
症状として次のようなものが挙げられます。
・呼吸困難
・呼吸が速くなる(※進行して呼吸抑制が起こる場合は呼吸が遅くなる)
・呼吸が浅くなる
・チアノーゼ(唇や指先が青紫色になる)
・冷や汗
・動悸
・意識障害
【参考情報】日本呼吸器学会『急性呼吸不全・ARDS』
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-01.html
Ⅰ型・Ⅱ型呼吸不全に共通して、酸素が取り込めず低酸素血症になるため、呼吸困難や頻呼吸、チアノーゼが起こります。
さらに低酸素状態が持続すると、多臓器不全が起こる可能性もあります。
Ⅱ型呼吸不全では二酸化炭素が排出できず蓄積するため、CO₂ナルコーシスにより意識障害や呼吸抑制が引き起こされます。
CO₂ナルコーシスとは、血液中の二酸化炭素濃度が異常に高くなることで中枢神経系や呼吸中枢が障害される状態のことです。
また、過剰な酸素投与が原因でCO₂ナルコーシスが起こる場合もあります。
例えばCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんの場合、慢性的に二酸化炭素濃度が高い状態に体が慣れています。
その状態で高濃度の酸素投与を行ってしまうと、呼吸中枢が酸素濃度が上がったと錯覚し、呼吸を抑制してしまうのです。
重症化すると、昏睡や呼吸停止など命に関わる症状が引き起こされるため、一刻も早く二酸化炭素を排出させる必要があります。
【参考情報】日本離床学会『Q&A Vol.86 CO2ナルコーシスでの意識障害』
https://www.rishou.org/for-memberships/qa/qa-vol-86#/
また、急性呼吸不全よりも速いスピードで起こる、重度の呼吸不全を「急性呼吸促迫症候群(ARDS)」と言います。
ARDSは、「急性・びまん性肺障害による重度の低酸素血症」と定義され、肺自体の炎症や損傷によってより重度の酸素不足に陥る状態を指します。
急性呼吸不全の中でも進行が早く、48時間以内に急速に進行するのが特徴です。
緊急性が高く、集中治療室で人工呼吸を用いた治療が必要になります。
【参考情報】日本集中治療医学会『ARDSの診療をご理解いただくために』
https://www.jsicm.org/publication/pdf/ARDSGL2021_GP.pdf
4.急性呼吸不全の原因

急性呼吸不全の原因は多岐にわたります。
1章で説明した「全身の臓器に酸素を届けるために必要な5つの働き」のどれか1つでも問題が起こると、呼吸不全を引き起こす原因となります。
具体的な原因には次のようなものがあります。
・肺炎、肺水腫、気胸、COPD、肺の外傷:肺がダメージを受け、ガス交換機能が障害されるため
・肺塞栓症:肺動脈が血栓で詰まることで、肺への血流が遮断されるため
・喘息発作:気道が狭くなり、換気ができなくなるため
・脳卒中や頭部外傷:呼吸中枢が障害されるため
・麻薬や睡眠薬の過剰摂取:呼吸が抑制されるため
・筋ジストロフィー、重症筋無力症、ギランバレー症候群:呼吸をする筋肉が動かなくなるため
・重度の貧血:酸素の運搬に支障が出るため
・循環血液量減少性ショック/心原生ショック:出血や心不全により全身に血液が回らず酸素不足になるため
・敗血症性ショック:血管拡張により組織への酸素供給が低下するため
急性呼吸不全はいきなり起こるため予防するのは難しいですが、基本的な感染症対策や禁煙、喘息の場合は治療の継続などが大切です。
5.診断・検査

急性呼吸不全が疑われる場合、次のような検査を行います。
5-1.問診、バイタルサインチェック
問診で既往歴や症状の経過を確認すると同時に、バイタルサインや意識状態などから緊急性を判断します。
意識レベルやSPO₂(酸素飽和度)の低下が見られる場合、唇や爪が紫色になるチアノーゼが見られる場合は、状況に合わせてすぐに酸素投与や人工呼吸管理を行います。
5-2.血液ガス分析
血液ガス分析とは、動脈血を採血して、PaO₂(動脈血酸素分圧)やPaCO₂(動脈血二酸化炭素分圧)を調べる検査です。
数値的に呼吸不全かどうか、またⅠ型・Ⅱ型のどちらなのかを判別するために行われます。
PaO₂とは、動脈血中にどれくらい酸素があるのかを表すデータです。正常値は80~100mmHgで、60mmHgを下回ると異常値になります。
簡単に言うと、「正常に息を吸えているか」を判断する指標になります。
PaCO₂は、動脈血中にどれくらい二酸化炭素があるのかを表すデータです。正常値は35~45mmHgで、45mmHgを上回ると異常値になります。
こちらは「正常に息を吐けているか」を判断する指標になります。
「PaO₂が低下しているものの、PaCO₂は正常」という場合は、肺のガス交換がうまくいかず、十分な酸素を取り込めないために低酸素血症(血中の酸素不足)が生じる状態ため、Ⅰ型呼吸不全にあたります。
「PaO₂は低下、PaCO₂は上昇」のように両方基準値から外れる場合は、酸素を取り込む力だけでなく、二酸化炭素を十分に排出する力も低下しているため、低酸素血症に加えて二酸化炭素が体内に蓄積してしまう状態のため、Ⅱ型呼吸不全に当たります。
呼吸不全であることが分かれば、原因疾患を特定するための検査を行います。
5-3.画像検査
呼吸不全の原因が肺疾患かどうかを確認するために、胸部X線検査(レントゲン)や胸部CT検査を行います。
例えば胸部X線検査では、次のような異常が見られることがあります。
・肺炎や肺水腫の場合→肺に白い影(浸潤影・すりガラス影)が見られる
・気胸の場合→肺が虚脱し、胸腔内に空気が見えるため黒く映る
異常がある場合は、より詳細な胸部CT検査を行います。
5-4.肺機能検査(スパイロメトリー)
呼吸不全の原因として喘息やCOPDが疑われる場合に行います。
スパイロメトリーは、「スパイロメーター」という機械を使って肺の換気能力を調べる検査です。
1秒量(FEV₁)が低下している場合は、COPDや喘息などの「閉塞性換気障害」の可能性があります。また、肺活量(VC)が低下している場合は、間質性肺疾患などの「拘束性換気障害」の疑いがあります。
5-5.血液検査
血液検査も、原因疾患の特定に役立ちます。
指標となる項目には次のようなものがあります。
・炎症反応(CRP・白血球): 肺炎・敗血症の評価
・心筋マーカー(BNP・トロポニン): 心不全・心筋梗塞の評価
・Dダイマー:肺塞栓症のスクリーニング
・Hb(ヘモグロビン):貧血による低酸素の評価
6.治療
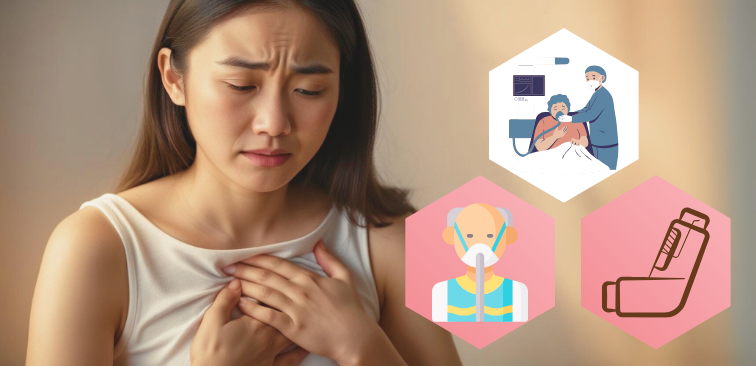
急性呼吸不全は緊急性が高いため、すぐに酸素投与や人工呼吸管理を行う必要があります。
また、同時に原因疾患の治療(肺炎なら抗菌薬、喘息なら吸入薬の投与など)も行います。
病院を受診する際は次の情報を伝えていただくと、診断の際に役立ちます。
ご本人が伝えるのが難しい場合は、付き添いの方が代わりに伝えられるようメモしておくとスムーズです。
・息苦しさの持続期間、発症スピード(いきなり苦しくなったのか少しずつ苦しくなったのか)
・発症時の状況
・安静にしていても息苦しさがあるか
・姿勢によって息苦しさに変化があるか(仰向けだと苦しいが、座っていると少し楽など)
・他の症状(胸痛、発熱、咳、痰、喘鳴の有無など)
・既往歴(喘息、COPDなど)
【参考情報】日本内科学会『呼吸困難(息苦しさ)』
https://www.naika.or.jp/wp-content/uploads/2015/05/commonspl1.pdf
7.おわりに
急性呼吸不全とは、突然、呼吸がうまくできなくなり、体内の酸素が不足する状態のことです。
血液中の酸素が極端に低下(低酸素血症)したり、二酸化炭素が溜まりすぎる(高二酸化炭素血症)ことで、呼吸困難や意識障害を引き起こします。
緊急性が高く、治療は一刻を争います。特に、意識レベルの低下やチアノーゼなどが見られる場合は、迷わず救急車を呼びましょう。





