COPD患者の家族ができるサポートと暮らしの工夫
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)
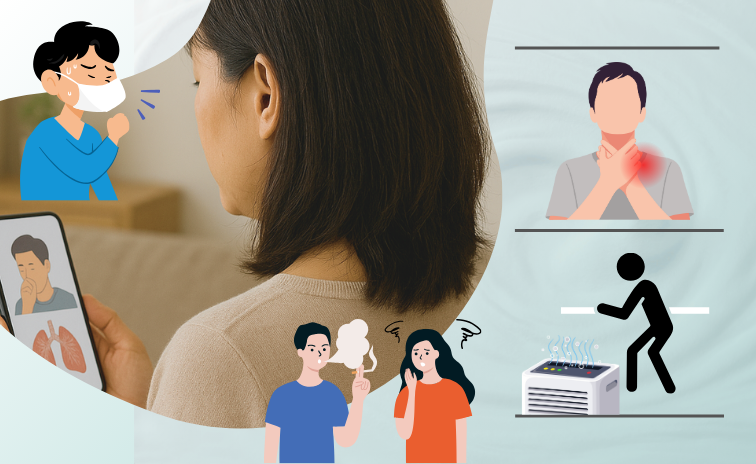
親や配偶者がCOPD(慢性閉塞性肺疾患)と診断されたとき、「どんなふうに支えたらいいんだろう」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
呼吸がつらそうな様子を見て不安になったり、どう声をかけていいのか悩んだり…。この記事では、患者さんと一緒に暮らすご家族が日常でできるサポート方法や、受診時のポイントをやさしく解説していきます。
1. COPDとは?知っておきたい基礎知識

身近な人がCOPD(慢性閉塞性肺疾患)と診断されると、不安を感じることもあると思います。
まずは病気の特徴を家族が理解することが大切です。正しい知識を持つことで、日常の接し方や環境づくりにも自信が持てるようになります。
1-1.COPDの症状理解と呼吸を楽にする基本的な方法
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、肺の働きが徐々に低下していく病気で、長年の喫煙習慣が主な原因です。
たばこの煙によって気道や肺胞に炎症が起き、息を吐き出す力が弱まり、呼吸のしづらさ、慢性的な咳や痰といった症状が現れます。
特に高齢者に多く、症状は最初は軽くても少しずつ進行します。主な症状は動いたときの息切れ、咳や痰の増加、疲れやすさなどで早めに気づくことが大切です。
また、風邪や気温の変化をきっかけに症状が急に悪化する「急性増悪(きゅうせいぞうあく)」があり、次のような変化が見られた場合は早めに医療機関に相談しましょう。
・息苦しさがいつもより強く感じる
・咳やたんの量・色が急に変わる
・熱がなくても全身のだるさが続く
症状を理解したうえで、息苦しさを和らげる方法も覚えておくと安心です。
家族ができるサポートとして、呼吸法を患者さんと一緒に練習しておきましょう。
口すぼめ呼吸(唇を軽くすぼめてゆっくり息を吐く)、腹式呼吸(お腹を膨らませるように鼻から吸い口から吐く)、前かがみの楽な姿勢(机やひざに腕を置く)などが効果的です。
これらの方法を息苦しいときに思い出せるようにしておくことで、患者さんの不安を和らげることができます。
◆『COPD(慢性閉塞性肺疾患)を知っていますか?』について>>
【参考情報】『慢性閉塞性肺疾患(COPD)』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/b/b-01.html
1-2. なぜ「家族の支援」が重要なのか
COPDは症状が進行する呼吸器の病気で、薬や治療だけでなく家庭での過ごし方や家族の支えが、症状の安定や患者さんの生活の質に大きく関わります。
症状が進行すると息切れや疲労感が強くなり、本人が体調の変化をうまく言葉にできないこともあります。そのとき、近くで過ごす家族が小さな異変に気づくことが早期対応につながります。
また、慢性の病気では心理的な不安や孤独感を抱える方も少なくありません。
安心できる生活環境と穏やかなコミュニケーションが、治療意欲や自己管理の継続にも前向きな影響を与えます。
COPDという病気についてさらに詳しく知りたい方は、下記の情報も参考にしてください。
【参考情報】『健康イベント&コンテンツ COPD(慢性閉塞性肺疾患)』厚生労働省
https://kennet.mhlw.go.jp/slp/event/disease/copd/index
2. 家庭内の空気環境を整えるポイント

COPD患者さんにとって、自宅の環境は症状の安定に直接関わります。
室温・湿度の急変や、たばこの煙、ホコリなどは気道を刺激し息苦しさを誘発する要因となります。
2-1. 温度管理と禁煙対策の基本
COPD患者さんにとって快適な環境づくりでは、温度管理と禁煙対策の両方が欠かせません。
冷たい空気や急な温度差が気道を刺激し、咳や息切れを引き起こします。家中の温度差を少なく保つため、次のような工夫を心がけましょう。
・部屋ごとの温度差を減らす(廊下や脱衣所にも暖房を設置)
・厚手のカーテンや断熱シートで窓際の温度差を防ぐ
・エアコンや扇風機の風が直接当たらないよう風向きを調整
・外出時はマフラーやマスクで口元を保温
また、季節別の目安温度は冬18~22℃、夏28℃前後が適切です。
温度管理と同じく重要なのが禁煙対策です。COPDの最大の原因は喫煙による肺ダメージのため、患者本人の禁煙と家族の協力が不可欠です。
たばこの煙には数百種類の有害物質が含まれ、受動喫煙は患者の症状悪化だけでなく家族の健康にも悪影響を及ぼします。
室内喫煙では煙が壁やカーテンに染み込み「三次喫煙」として長期間有害物質が残存するため、家の中では完全禁煙が最も確実な対策です。
家族に喫煙者がいる場合は、責めるのではなく「協力して一緒にやめよう」という声かけが効果的です。
【参考情報】『ぜん息・COPDにおける四季のケア』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/54/feature/
【参考情報】”Smoking and COPD” by Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/copd.html
2-2. 湿度と空気質の管理
湿度が高すぎても低すぎても呼吸に影響しやすく、目安としては40~60%程度を保つことが望ましいとされています。
加湿器・除湿器・空気清浄機などを活用し、湿度コントロールと浮遊粉塵・アレルゲン除去に努めましょう。特に花粉、カビ、ダニ、ホコリなど刺激になる物質をなるべく排除することが大切です。
定期的な換気も重要ですが、外気中の大気汚染や黄砂・花粉などが激しい時は換気回数を控える判断も必要です。
3. 息切れや体調悪化に気づいたときのケアと対応

COPD患者さんは、気温や体調、日常動作の変化で息苦しさを感じやすくなります。そんなとき、家族が落ち着いて適切に対応できることが安心と安全につながるでしょう。
ここでは「息苦しさのケア」「受診の目安」「緊急時の備え」の3つの視点から、家庭でできるサポートをご紹介します。
3-1. 息苦しさを感じたときの声かけと支え方
息苦しさが強くなったとき、何より大切なのは落ち着くことです。焦りや不安で呼吸が浅く速くなると、さらに苦しく感じてしまいます。
家族がそばで冷静に声をかけることで、患者さんの呼吸を整える助けとなります。
「少し休もうか」「大丈夫、ゆっくりでいいよ」といった短くやさしい言葉で穏やかな空気をつくりましょう。「頑張って!」という励ましは悪気がなくてもプレッシャーになるため避けた方が安心です。
息苦しいときは、前かがみの姿勢や口すぼめ呼吸などの呼吸法を思い出して一緒に行いましょう。
姿勢や呼吸を助ける際は「一緒にやってみようか」と声をかけながら、本人のペースを尊重し、無理なく行うことが大切です。
【参考情報】『【実践編】口すぼめ呼吸』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/effective/03.html
3-2. 症状に変化を感じたら受診のサイン
1-1でご紹介した急性増悪のサインに加えて、家族が日常で気づく小さな変化も重要です。
「顔色がすぐれない」「いつもより疲れやすい」「食欲がない」といった違いは、本人よりも家族の方が気づきやすいものです。症状の変化に気づいたら「もう少し様子を見よう」ではなく、早めの受診を検討しましょう。
風邪だと思っていたものが実は増悪のサインであることもあり、初期対応の遅れは呼吸機能低下を招くおそれがあります。
受診時は、いつからどんな変化があったかを簡単にメモして伝えると診察がスムーズになります。「いつもと違う」と感じたら、それは家族だからこそ気づけるサイン。その一言が患者さんを守る大切なきっかけになります。
3-3. 緊急時の対応と事前の備え
症状が急激に悪化した場合は、ためらわずに救急要請(119番)を行いましょう。次のような状態は命に関わる可能性があります。
・話すのが難しいほど息苦しい
・唇や指先が紫色になる(チアノーゼ)
・意識がもうろうとしている
・強い胸の痛みや動悸がある
緊急時に備えて、かかりつけ病院の連絡先を掲示し、薬や診察券、保険証をまとめて保管しておきましょう。
酸素療法中の方は使い方を家族全員で共有し、救急隊への情報(持病・薬・アレルギー)をメモしておくことも必要です。
患者さんが不安にならないよう、家族が落ち着いた声で話しかけることも忘れないでください。
【参考情報】”COPD — Know When to Go to the ER” by Emergency Physicians Association
https://www.emergencyphysicians.org/article/know-when-to-go/COPD
4. 日常生活を支えるためのサポートと工夫

COPD患者さんが穏やかに日常を過ごすためには、生活の中の小さな工夫が欠かせません。
ここでは食事、入浴、移動といった日常動作のサポート方法をご紹介します。
4-1. 食事をサポートするときの工夫
COPD患者さんは食事中にも呼吸の負担を感じやすく、息が苦しくなると食欲が落ち、体力低下を招くこともあります。
食事の際は「焦らず、少しずつ」を心がけ、1回の食事量を少なめにして回数を分けると呼吸への負担を軽減できます。食べ物は柔らかく調理し、たんぱく質を意識して摂ることで筋肉の維持にもつながります。
食後すぐに横になると胃がふくらんで呼吸が苦しくなるため、食べ終わったあとは椅子に座って少し休んでから横になりましょう。
また、COPD患者さんの中には「食べ物の味がしない」「食欲がわかない」という症状を訴える方もいるため、このような変化に気づいたら早めに相談することが大切です。
【参考情報】『【実践編】食事を見直す』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/nutrition/03.html
【参考情報】”Nutrition and COPD” by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/copd/living-with-copd/nutrition
4-2. 身の回りのケアと移動サポート
入浴は湯気が負担になることがあるため、短時間で済ませるか半身浴・シャワーを活用しましょう。体を洗うときは座って行うと呼吸が楽になります。
移動や外出では「本人のペースに合わせること」が最重要です。歩くスピードをゆっくりにし、こまめに休憩を取ることで息苦しさを防げます。家の中では手すりを設けて転倒を防ぎ、動線を広く保つと移動がスムーズになります。
酸素療法中の方はチューブの位置やボンベ残量を確認し、外出時は天気や気温変化も考慮しましょう。咳が長引く場合は、いつまで様子を見るべきか、受診の目安を家族が把握しておくことも安心につながります。
5. 家族が安心して関わるために知っておきたいこと

COPDは長い時間をかけて付き合っていく病気です。一方で、支える側のご家族も不安や疲れを感じることがあるでしょう。
ここでは、患者さんと向き合ううえで知っておきたい考え方をご紹介します。
5-1. 家族が”無理をしない支え方”を心がける
COPDは「治す」病気ではなく、進行をゆるやかにして上手に付き合っていく病気です。
気温の変化や風邪、ストレスがきっかけで症状が強くなることがあり、そうした特徴を理解しておくことで慌てずに対応できるようになります。
支える時間が長くなると、家族の方も疲れやストレスを感じることがあります。「私が頑張らなきゃ」と思う気持ちは大切ですが、無理をしすぎると長く続けることが難しくなります。
支え方の基本は、できる範囲で関わることです。完璧を目指すより「今日はここまででいい」と思える気持ちの余裕を持つことが大切です。一人で抱え込まず、ほかの家族や友人、医療スタッフ、訪問看護などにも頼りながら支え合いましょう。
家族自身がリフレッシュできる時間を持つことも忘れないでください。散歩をしたり、好きな音楽を聞いたり、コーヒーをゆっくり飲むだけでも心が整います。家族が元気でいることは患者さんにとっていちばんの安心です。
5-2. 不安を共有し、支え合える関係づくりを
COPDは患者さん本人だけでなく、家族みんなで向き合う病気です。お互いの気持ちを話し、共有することが大切です。
体調のことや不安に思うことなど、少しずつでも言葉にして話し合うことで誤解が減り、支え合いやすい関係が生まれます。家族の中でも素直に疲れやつらさを言い合える空気があると安心です。
また、医師や看護師に質問することをためらわないでください。病気のことや生活の工夫など、医療スタッフに相談することで心の負担が軽くなることもあります。
特に呼吸器内科の専門医やスタッフは、COPD患者さんとご家族が抱える悩みを多く理解しており、実践的なアドバイスを得やすい環境があります。
支えるのは一人ではなく、みんなで。頼り、相談してもいいんだと思える関係が、長く続く支えになります。
6. おわりに
COPDは長く向き合っていく病気だからこそ、治療と合わせて家族の日々の支えが患者さんの安心につながります。部屋の空気を整えたり、声をかけたり、そっと寄り添ったり。そのひとつひとつが大きな励ましとなります。
一方で、支える家族もまた自分自身の時間や心の健康を大切にしてください。無理をせず「今日はこれでいい」と思える日があってもかまいません。家族が笑顔でいられることが、患者さんにとって何よりの安心です。
完璧に支えようとしなくても大丈夫。穏やかに寄り添う気持ちこそが、COPDと向き合う力になります。





