喘息予防に効果的な家庭での掃除方法
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)

喘息はホコリやダニ、花粉などで症状が悪化しやすく、家庭内の掃除が大きな影響を与えると考えられます。
ところが「掃除をすれば安心」と思い込むと、かえってアレルゲン(アレルギー反応を起こす原因となる物質)を撒き散らし、吸い込んでしまう危険もあります。
喘息をお持ちのご家族と暮らす家庭では、どんな工夫が必要なのでしょうか。
1. 空気中にアレルゲンが広がる場面を知る

掃除は本来きれいにするための行為ですが、やり方次第ではアレルゲン(ダニ・カビ・ハウスダスト・花粉・ペット由来の皮膚片など)が空気中に広がり、喘息をお持ちのご家族が症状を起こしやすい環境になってしまいます。
まずはホコリなどのアレルゲンが「舞いあがりやすい場面」を知って、換気・湿度管理・掃除の順序を意識しましょう。
1-1 布団やカーペットを叩くとき
布団やカーペットを強くたたくと、中にいるダニやそのフンが空気中に広がってしまいます。なので、布団はたたくのではなく、よく日に干してから表面を丁寧に掃除機で吸うのが良いとされています。
寝具全体は防ダニカバーの使用や定期的な洗濯を心がけ、清潔を保って寝室のアレルゲン負担を減らしましょう。
1-2 掃除機をかけるとき
掃除機の使用時や紙パック交換・ごみ捨ての瞬間はホコリが舞いあがりやすく、吸い込んでしまう危険性が高まります。窓を開けて換気し、マスクを着用して作業しましょう。
床面は、掃除機の前に水拭きをして乾いてから行うなど、拭き掃除と組み合わせるとホコリを抑えられます。出たごみはビニール袋で密閉し、なるべく早めに処分できると安心です。
1-3 換気が不十分なとき
換気が不足すると、舞い上がったアレルゲンが室内にとどまります。掃除の前後には窓を開け、浴室や台所は換気扇を積極的に使用してください。
あわせて室内湿度はおおむね60%以下が目安です。
押し入れ・北側の部屋・観葉植物や水槽など湿気のたまりやすい要因にも注意し、季節や住んでいる環境に応じて除湿・日当たり・通気を確保しましょう。
【参考情報】『健康・快適居住環境の指針』東京都保健医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/zenbun3
2. 掃除する人も油断できない理由

「自分は喘息ではないから大丈夫」と思っていても、掃除をする人がアレルゲンを持ち込み、無意識のうちに家全体に広げてしまうことがあります。
アレルゲンは目に見えない微細な粒子のため、気づかないうちに家族に影響を及ぼすのがやっかいな点です。
2-1 衣服や髪に付着して持ち歩く
掃除で舞い上がったホコリやダニ、花粉は衣服や髪に付着しやすく、そのまま移動すると他の部屋にも広がってしまいます。
特に布団やカーペットを扱った直後は付着量が多くなるため注意が必要です。
掃除の際は、外出着のまま行わずエプロンを着用したり掃除用の服に着替え、長い髪はまとめてバンダナなどを三角巾のようにかぶると安心です。
【参考文献】”Dust Mites” by American Lung Association
https://www.lung.org/clean-air/indoor-air/indoor-air-pollutants/dust-mites
2-2 ごみ捨ての際は要注意
掃除機の紙パック交換やダストボックスのごみ捨て時にも、大量のホコリが一気に舞い上がります。
このときに吸い込む量は掃除中より多いこともあり、窓を開けて換気をしながら作業することが大切です。
ごみはビニール袋で密閉し、できるだけ早めに処分できるといいでしょう。
2-3 掃除をする人の健康への影響
アレルゲンは喘息をお持ちのご家族だけでなく、健康に見える人にも長期的な影響を与える可能性があります。
繰り返し吸い込むことで咳や鼻炎などの症状が出ることもあるので、掃除を担当する人自身も防御が必要です。マスク・手袋・眼鏡などを活用し、吸入や皮膚への付着を減らしましょう。
【参考情報】『住まいの環境整備と喘息対策』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/control/measures/indoor.html
3. 掃除中に気をつけたいこと
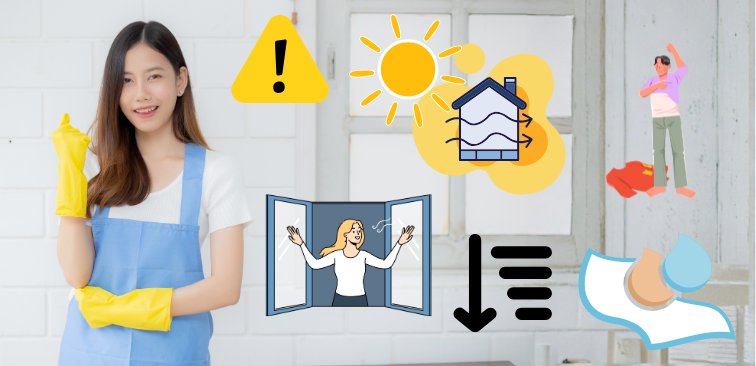
掃除の仕方や進め方を少し工夫するだけで、喘息をお持ちのご家族の負担を減らすことができます。
ここでは掃除そのものに関する具体的に配慮したい点を紹介します。
3-1 掃除を始める時間帯の工夫
掃除は朝や日中など換気しやすい時間帯に行うのが理想です。夜に掃除をすると窓を開けにくかったり、音を気にして掃除機をかけられなかったりして、ホコリが残ったまま就寝することにつながります。
ついやってしまいがちな例として「帰宅後すぐ掃除を始める」ことがありますが、それでは衣服についた花粉やホコリを室内に広げてしまいます。改善策として、帰宅後はまず着替えてから掃除に取りかかると安心です。
ただしご家庭によっては夜しか掃除できない場合もあるでしょう。そのときは後述のように、窓を少しだけ開けて換気扇や空気清浄機を併用したり、掃除道具の工夫などでホコリの舞い上がりを減らせます。
3-2 換気と掃除を組み合わせる
掃除の前後だけでなく、途中で窓を開ける・換気扇を回すなど、作業中にもこまめな換気を取り入れましょう。
寒い時期や短い時間の掃除だと、うっかり窓を閉め切ったまま作業してしまいがちですが、これではアレルゲンが部屋にとどまってしまいます。
3-3 掃除の順序を守る
部屋を効率的に清潔にするには、「上から下へ」「奥から入口へ」と進めるのが基本です。思いついた場所から手をつけると、ホコリが再び落ちてしまい、二度手間になることがあります。
3-4 使用する道具の工夫
乾いたハタキやモップはホコリを舞い上げやすいため避け、湿らせた布や水拭きシートを使うと安心です。
乾拭きだけで済ませてしまうのは手軽ですが、かえって空気を汚してしまう原因になります。
【参考情報】『アレルギー疾患生活環境改善の手引き』日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/stwn/index.php?content_id=2
【参考文献】”Allergy-proof your home” by Mayo Clinic Staff
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/allergies/in-depth/allergy/art-20049365
4. 掃除で工夫できる具体的なポイント

掃除はやり方だけでなく、どこを重点的に清潔に保つかが重要です。
ここでは、特にアレルゲンがたまりやすい場所や物に注目した工夫を紹介します。
4-1 寝具やカーテンの洗濯
寝具やカーテンはダニやホコリの温床になりやすい場所です。
シーツを長期間取り替えずに使い続けると、寝ている間にアレルゲンを吸い込みやすくなります。
週1回を目安に洗濯し、しっかり乾燥させることが勧められています。
4-2 床や棚の拭き掃除
床や棚の上はホコリがたまりやすく、乾いた布で拭くだけでは空気中に舞い上がってしまいます。
短時間で済ませたつもりでも、後から咳やくしゃみを引き起こす原因になります。
湿らせた布や水拭きシートを使用することで、舞い上がりを抑えながらしっかり取り除けます。
4-3 湿気の多い場所の管理
浴室や押し入れ、北側の部屋は湿気がこもりやすく、放置するとカビやダニが増える原因となります。
入浴後に換気扇をすぐ止めてしまうと、湿気が残ってしまいます。
30分以上換気扇を回す、除湿器を活用するなど、十分な湿気対策を心がけましょう。
◆「喘息やアレルギー症状の悪化を防ぐ!カビの掃除で気を付けるポイント」>>
4-4 家具やカーペットの扱い
厚手のカーペットや布張りのソファはホコリをため込みやすく、掃除機だけでは内部の汚れを取り除けません。
敷きっぱなしのカーペットはダニが増える原因になります。
丸洗いや日干しを定期的に行う、取り外し可能なカバーを選ぶことで清潔を保ちやすくなります。
【参考情報】『減らそう!ダニアレルゲン』江戸川区
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e055/kenko/eisei/kankyo/sumaieisei/eiseigaichu/dani.html
5. 家族で決めたい掃除ルール

掃除は一人だけの努力では続きにくく、家族全員が同じ意識を持つことが大切です。
ルールを共有することで負担が分散され、日常的に清潔な環境を保ちやすくなります。
5-1 家族の症状に配慮した掃除タイミング
掃除中はホコリが舞いやすいため、喘息をお持ちのご家族が部屋にいない時間に行うと安心です。
学校や仕事で外出している間に掃除する、または別の部屋で過ごしている間に済ませるなど、生活のリズムに合わせて工夫しましょう。
喘息と鼻炎を両方持っている方は、掃除のときに出るホコリなどの刺激で、どちらの症状もひどくなることがあります。そのため、掃除の仕方や環境により気をつけて工夫することが大切です。
5-2 掃除の仕方や基準を確認する
家族によって「きれい」と思う基準が異なると、掃除の効果に差が出ます。
拭き掃除は湿らせた布で行う、掃除後は一定時間換気を続けるなど、やり方を話し合って共通の認識を持つことが大切です。
5-3 寝具やカーテンの管理を分担する
寝具やカーテンの洗濯は後回しになりやすいため、週1回を目安に担当を交代しながら実施すると継続しやすくなります。
予定をカレンダーに記入しておくと忘れにくくなります。
5-4 掃除後の行動を決めておく
掃除直後はホコリがまだ漂っています。すぐに戻らず、30分ほど換気を続けてから部屋に入るようにすると安心です。
タイマーやアラームを使って換気の残り時間を見えるようにすると、家族全員で守りやすくなります。
5-5 症状が強いときの対応を話し合う
発作や咳が出たときに慌てないよう、薬の使用方法や受診の目安を家族であらかじめ確認しておくことが大切です。
誰がどのように対応するかを共有しておけば、緊急時にも落ち着いて行動できます。
6. おわりに
喘息をお持ちのご家族と暮らす日常では、掃除の工夫が大きな支えになります。
布団やカーテンの管理、床や棚の拭き掃除、湿気対策など、ひとつひとつは小さな工夫ですが、積み重ねることで安心できる住環境につながります。
大切なのは、家族全員が同じ認識を持ち、ルールを共有して協力することです。生活の中で自然に取り組める工夫を続けることで、無理なく清潔な環境を維持できます。
【参考情報】『室内の環境整備とアレルゲン対策』東京都保健医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/web_arerugen_taisaku_kenkai_sisin





