お風呂で喘息が悪化する理由と対策について解説
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)
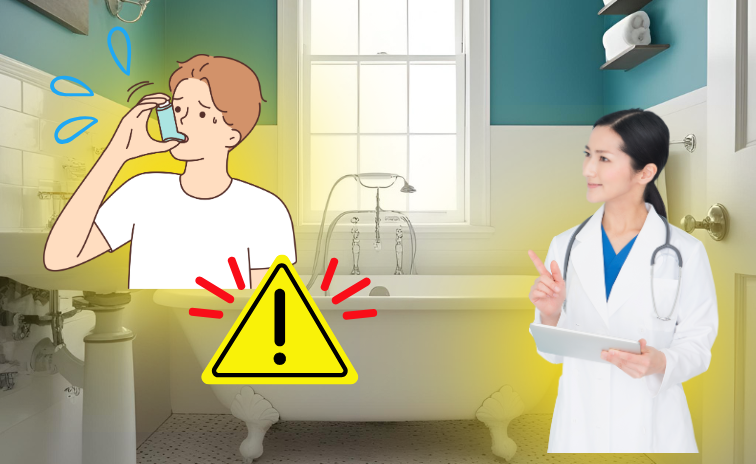
入浴は清潔を保つために欠かせないもので、「健康に良いこと」というイメージが強いのではないでしょうか。
特に湯船につかると、リラックス効果や血行促進など様々な健康効果も期待できます。
しかし、喘息の患者さんにとっては、入浴が喘息症状を悪化させる場合もあります。
発作時に無理をして入浴しないのはもちろん大切ですが、症状が安定している時であっても注意が必要です。
この記事では、喘息の患者さんが入浴時に気をつけるべきポイントについて詳しくご説明します。
1.喘息悪化の主な原因とは?

喘息の患者さんの気道は、症状がない時でも慢性的な炎症が起こっている状態です。
そこに様々な刺激が加わることで、発作的に咳や「ゼーゼー」「ヒューヒュー」のような喘鳴、呼吸困難などの症状が起こります。
喘息悪化の原因となる刺激には次のようなものがあります。
発作が起こらないようコントロールするためには、これらの刺激をなるべく避けて生活することが大切です。
【参考情報】日本呼吸器学会『気管支ぜんそく』
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/c/c-01.html
1-1.アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)
アレルゲンには、ダニ、カビ、ペットの毛、花粉、食物などがあります。
アレルゲンが体内に入ると、異物を排除しようとする免疫の働きによってアレルゲンに対するIgE抗体が作られます。
IgE抗体がマスト細胞(皮膚や粘膜にある細胞)に結合することでアレルゲンに反応しやすい状態(感作)が作られます。
その後、再びアレルゲンが体内に侵入すると、マスト細胞が活性化し、ヒスタミンなどの物質を放出してアレルギー症状を引き起こします。
このようにヒスタミンをはじめとする炎症性物質が気道に炎症を引き起こし、気道が狭くなることで喘息が悪化するのです。
1-2.呼吸器感染症
ただでさえ刺激に敏感になっている喘息患者さんの気道に、ウイルス感染による炎症が加わることで喘息が悪化してしまいます。
また、ウイルスを排除するために免疫機能が過剰に活性化し、炎症性物質が大量に放出されることも喘息悪化の原因になります。
風邪やインフルエンザに罹らないよう、マスクの着用や手洗いうがい、予防接種などの感染予防行動を行いましょう。
1-3.気候の変化
喘息症状は天気や気温・気圧の変化にも左右されやすく、季節としては春や秋に、1日の中では夜中から明け方にかけて症状がひどくなりやすいという特徴があります。
春や秋は気圧変動や朝晩の温度差が大きい季節です。また、花粉などのアレルゲンの増加や感染症に罹りやすい時期でもあるため、特に注意が必要です。
冷たい空気や乾燥した空気は気道を刺激するため、夜中から明け方に症状が悪化しやすくなります。
気道への刺激を減らすためには、加湿器やマスクなどを使って加温・加湿することが大切です。
気候や季節の変化は避けることができませんが、あらかじめ薬を貰っておくなど喘息悪化に備えておきましょう。
1-4.その他
喘息悪化の原因には、他にも次のようなものがあります。
・運動
・喫煙
・アルコール
・肥満
・薬に含まれるアスピリン
・ストレス・過労
・月経や妊娠
◆『お酒を飲むと咳が止まらない。アルコール誘発喘息とは』>>
喘息悪化の原因となるものは、日常生活のいたるところに隠れています。
どのような環境の時に喘息発作が起こりやすいかなど、「ぜんそく日記」などにメモして把握しておくことも大切です。
【参考文献】”Asthma” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/symptoms-causes/syc-20369653
2.お風呂で喘息が悪化する理由と対策について

では、お風呂場では具体的にどのような所に注意すれば良いのでしょうか。
お風呂場で喘息が悪化する原因と、その対策について紹介します。
2-1.カビ
カビは「湿度」「温度」「栄養」が揃った場所で発生しやすいと言われています。
お風呂場は湿度や温度が高く、皮脂汚れや石鹸カスなどの栄養もあるため、カビが発生しやすい環境にあります。
特に黒カビは目に見える形で壁や天井に現れるだけでなく、目に見えないカビの胞子が空気中に浮遊していることもあります。
このカビの胞子を吸い込むことでアレルギー反応が起こり、喘息症状が悪化する可能性もあるため注意が必要です。
【参考情報】Mayo Clinic “ Mold allergy”
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mold-allergy/symptoms-causes/syc-20351519
<カビ対策のポイント>
・湿気対策
:入浴後は必ず換気扇を回し、窓やドアを開けて湿気を逃がしましょう。
また、壁や床に水分が残っている状態ではカビが発生しやすいため、入浴後にタオルで水分を拭き取るのも効果的です。
・定期的な掃除
:湯船や床、壁などはもちろんですが、天井にもカビの胞子が付着していることがあるため、定期的に掃除しましょう。
・防カビ対策グッズの活用
:防カビ燻煙剤や、カビ予防シートなどのグッズを活用するのもおすすめです。
カビを完全になくすことは難しいですが、こまめに掃除をして清潔な状態を保ちましょう。
2-2.カビ取り剤
カビ取り剤や漂白剤の中には、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系成分を含むものがあります。
強力な洗浄力でカビを除去する一方で、特有の刺激臭をもつ塩素ガスを発生させることがあります。
喘息の患者さんがこの塩素ガスを吸い込むと、敏感になっている気道がさらに刺激され、咳や息苦しさ、ひどい場合には喘息発作を引き起こす恐れがあります。
実際に、漂白剤を使用して健康被害があった人の中では「塩素系」が最も多く、喘息が悪化したケースも報告されています。
【参考情報】厚生労働省『家庭用品等に係る吸入事故等に関する報告』
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1226-1f.html
カビ取り剤や漂白剤は、健康な方でも具合が悪くなったり、他の洗剤と混ぜてしまうことで有毒ガスが発生してしまったりする場合もあります。
カビ取り剤を使用する際には使用上の注意をよく読んでから、マスクを着用し、十分に換気をしながら行いましょう。
体調があまりよくない時や、カビが頑固で取れない時は、専門の業者に依頼することも検討しましょう。
【参考文献】”Women using bleach for home cleaning are at increased risk of non-allergic asthma” by National Library of Medicine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27492540/
2-3.入浴剤
入浴剤は、リラックス効果や肌への保湿作用などがあります。
一見喘息とは関係がないように見えますが、人によっては喘息が悪化する可能性もあるため注意が必要です。
喘息の方が入浴剤を使用する際に注意するべきポイントは2つあります。
・香り
:合成香料や天然香料(エッセンシャルオイルなど)のような強い香りは、喘息の患者さんにとっては刺激になる場合があります。
・成分
:合成香料、エッセンシャルオイル、保存料(パラベンなど)、着色料は、人によってはアレルギー反応を引き起こすため、蒸気と一緒に成分を吸い込むことで喘息の症状を悪化させることがあります。
入浴剤を使用する際には成分を確認し、なるべく香料や着色料などを含まない入浴剤を選びましょう。
使用後に咳が出始めるなど、変わったことがあればすぐに使用を中止してください。
2-4.湯気
「冷たい空気を吸い込むと気道が刺激されて喘息が悪化する」ということをお伝えしましたが、刺激になるのは冷たい空気だけではありません。
適度に加温・加湿された空気を吸い込むと、痰の粘調性が低下して呼吸が楽になることもあります。
しかし湯気のような、気温・湿度ともに高い水蒸気を吸い込むと、気道が過剰に反応して収縮する場合があります。
これによって気道が狭くなり、喘息症状が悪化する原因になります。
湯気を吸い込まないというのは難しいですが、吸入ステロイド薬などの毎日の服薬を欠かさず行うことで、発作が起こりにくくなります。
2-5.リラックス/長風呂
気道が狭くなるメカニズムには、自律神経も深く関わっています。
自律神経とは、人間の体の無意識な働きを調整する神経で、「交感神経」と「副交感神経」があります。
交感神経は活動時に優位になり、気道では筋肉が緩んで呼吸がしやすい状態になります。
副交感神経はリラックスしている時に優位になります。一方で気管支平滑筋を収縮させる作用もあり、気道が狭くなることがあります。
リラックスしている夜間に喘息症状が悪化しやすいのは、副交感神経が優位になっていることも原因の一つです。
同じくリラックスしている入浴時には副交感神経が優位になるため気道が狭くなりやすい状態になります。
喘息患者さんの場合、この気道収縮が喘息発作を引き起こす原因となることがあります。
特に長風呂をすると体が過度にリラックスしてしまい、副交感神経の働きが強くなることで気道が狭くなるリスクが高まります。
入浴時に喘息の症状が悪化しやすい方は、長風呂は避けなるべく短時間で上がるようにしましょう。
2-6.寒暖差
寒暖差は気道を刺激し、喘息を悪化させる場合があります。
特に冬は、脱衣所の冷たい空気とお風呂場のあたたかい空気で、大きな温度変化が生じます。
入浴時の急激な温度変化は喘息を悪化させる可能性があるだけでなく、健康な人でもヒートショックを起こすリスクがあります。
ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が乱高下し、心臓や血管に大きな負担をかける状態のことです。
寒暖差は体にとって大きな負担になりますので、脱衣所を温めるなどして温度変化を極力減らしましょう。
3.お風呂前後には、十分な水分補給が必要

入浴中は体温が上昇するため汗をかき、体から水分が失われてしまいます。
すると喉や気道の粘膜が乾燥しやすくなり、気道に炎症や収縮が起こりやすくなるため、喘息症状が悪化する場合があります。
入浴前や入浴後は意識的に水分補給をするようにしましょう。
冷たい飲み物を飲んでしまうと喉への刺激になってしまうため、できれば常温か温かい飲み物がおすすめです。
4.おわりに
喘息発作を起こさず良好なコントロールを保つためには、通院・治療の継続や毎日の服薬に加えて日常生活管理も大切です。
アレルゲンや冷たい空気など、喘息を悪化させる可能性があるものはなるべく避けましょう。
入浴はリラックス効果や血行促進など様々な健康効果も期待でき、リフレッシュにもなります。
しかし喘息の患者さんは症状が悪化する場合もあるため、環境を整えてお風呂時間を快適に過ごせるようにしていきましょう。
入浴中に症状が悪化しやすいと感じる方は、脱衣所など近くに吸入薬を置いておくのもおすすめです。
発作で苦しい時や体調が優れないときは、無理に入浴せず安静にしましょう。





