コロナ禍が残した影?在宅勤務が招く睡眠時無呼吸症候群のリスクと今すぐできる対策
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)
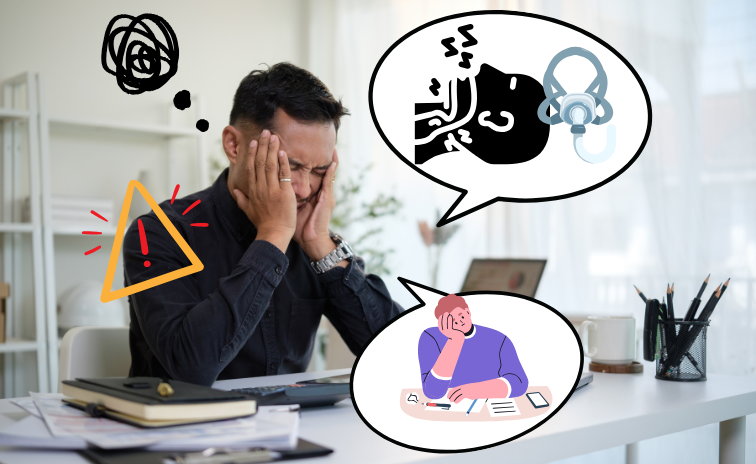
在宅勤務が続く中で、「しっかり寝ているのに疲れが取れない」「朝起きた時に頭がぼーっとする」といった症状、もしかして心当たりはありませんか?
実は、コロナ禍による生活の変化が、気づかないうちに睡眠時無呼吸症候群を悪化させるリスクを高めているかもしれません。
本記事では、在宅勤務が私たちの体に与える影響と、今日から実践できる対策方法をご紹介します。
1. 睡眠時無呼吸症候群とコロナ禍の関係

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりを繰り返す病気です。
この病気は、日中の眠気や集中力低下だけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高める深刻な疾患です。
【参考文献】”Obstructive sleep apnea associated with increased risks for long COVID” by National Institutes of Health (NIH)
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/obstructive-sleep-apnea-associated-increased-risks-long-covid
1-1 コロナ禍による生活変化の影響
新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの方が在宅勤務やリモートワークを経験されました。この生活様式の変化は、睡眠時無呼吸症候群の発症や悪化に大きく関わる要因を増加させています。
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、リモートワークが睡眠に及ぼす影響について、現時点では科学的知見が不十分であると述べています。
しかし、一般的に運動不足や生活リズムの乱れは睡眠の質に影響を与えることが広く知られており、コロナ禍での変化があなたの睡眠に影響を与えていないか、注意深く見つめ直す必要があります。
【参考情報】『健康づくりのための睡眠ガイド2023』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
1-2 睡眠時無呼吸症候群の基本的な症状
睡眠時無呼吸症候群の主な症状には、家族から指摘されることの多い大きないびき、夜間の頻尿、朝の頭痛、日中の強い眠気などがあります。
これらの症状は、在宅勤務中に「疲れているだけ」「寝不足のせい」と見過ごされがちですが、放置すると重大な健康問題につながる可能性があります。
日本呼吸器学会の診療ガイドライン2020によると、50歳代では男性の約10~20%、女性の約10%弱が睡眠関連呼吸障害を患っており、症状を伴う睡眠時無呼吸症候群は男性約5%、女性約2~3%に見られるとされています。
◆『更年期の疲労感の原因はいびき?睡眠の質を改善する方法を解説』>>
【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/publication/file/guidelines_sas2020.pdf
【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/i/i-05.html
2. 在宅勤務が引き起こす体重増加のリスク

在宅勤務の普及により、多くの方が体重増加を経験されています。
体重の増加は、睡眠時無呼吸症候群の最も重要な危険因子の一つです。
2-1 肥満と睡眠時無呼吸症候群の関係
日本呼吸器学会のガイドラインによると、肥満は睡眠時無呼吸症候群の最大の危険因子とされています。
体重が10%増加すると、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクが6倍になることが報告されています。これは、例えば体重が70kgの方が7kg増えるだけで、症状が大幅に悪化する可能性があることを意味します。
肥満により首回りや舌の周囲に脂肪が蓄積すると、気道が狭くなり、睡眠中の呼吸が妨げられやすくなります。
特に内臓脂肪型肥満(お腹周りの肥満)は、睡眠時無呼吸症候群のリスクをさらに高めることが知られています。
【参考文献】”Interactions Between Obesity and Obstructive Sleep Apnea” by A Romero-Corral et al. (PMC / NIH)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3021364/
2-2 在宅勤務による体重増加の要因
在宅勤務により体重が増加する主な要因には以下のようなものがあります。
まず、通勤時間がなくなることで、日常的な歩行量が大幅に減少します。
また、自宅にいることで間食の機会が増え、カロリー摂取量が増加しがちです。あなたにも心当たりはありませんか?
さらに、会議がオンラインになることで、長時間座ったままの状態が続きやすくなります。厚生労働省の研究によると、テレワーク実施者は身体活動量が減少し、座位時間が長くなる傾向があることが報告されています。
【参考情報】『テレワークの常態化による労働者の筋骨格系への影響や生活習慣病等への影響に関する研究』厚生労働省
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2022/202223016A.pdf
3. 運動不足が睡眠の質に与える影響

運動不足は、睡眠時無呼吸症候群を悪化させる重要な要因の一つです。
適度な運動は、睡眠の質を改善し、体重管理にも効果的です。
3-1 運動不足による睡眠への悪影響
運動不足は、筋力低下や心肺機能の低下を引き起こします。
特に上気道周囲の筋力が低下すると、睡眠中に気道が閉塞しやすくなり、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まります。
また、運動不足により自律神経のバランスが乱れると、深い眠りが得られにくくなり、睡眠の質が低下します。これにより、日中の疲労感や集中力低下が生じ、仕事のパフォーマンスにも影響を与える可能性があります。
3-2 在宅勤務中の運動不足解消法
在宅勤務中でも実践できる運動不足解消法をご紹介します。
まず、1時間に1回は席を立ち、軽いストレッチや室内歩行を行うことが大切です。
階段の昇降運動や、その場での足踏み運動も効果的です。タイマーを設定して、意識的に体を動かす習慣をつけましょう。
また、オンライン会議中でも、カメラに映らない下半身を使った運動を取り入れることができます。
足首の回転運動やふくらはぎの筋肉を意識した運動は、血流改善にも効果があります。例えば、ふくらはぎの上げ下ろし運動は、座ったままでも手軽に行えます。
4. 生活リズムの乱れと睡眠時無呼吸症候群
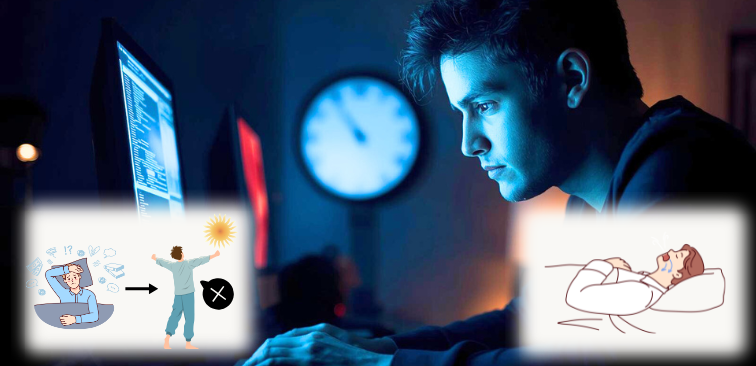
在宅勤務により生活リズムが乱れることも、睡眠時無呼吸症候群の悪化につながる要因の一つです。
規則正しい生活リズムを維持することは、良質な睡眠を確保するために重要です。
4-1 生活リズムの乱れが引き起こす問題
在宅勤務により、起床時間や就寝時間が不規則になりがちです。
また、通勤時間がなくなることで、朝の光を浴びる機会が減少し、体内時計が乱れやすくなります。これにより、夜間の睡眠の質が低下し、睡眠時無呼吸症候群の症状が悪化する可能性があります。
さらに、在宅勤務では仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちで、夜遅くまで仕事をしてしまうことも多くなります。
これが睡眠時間の短縮や睡眠の質の低下につながることがあります。仕事とプライベートの境界を意識的に設けることが重要です。
4-2 生活リズムを整える方法
生活リズムを整えるためには、まず毎日同じ時間に起床し、朝の光を浴びることが重要です。
可能であれば、朝の散歩や庭での作業など、屋外で過ごす時間を作ることをお勧めします。
また、就寝前のスマートフォンやパソコン、テレビなどの画面を見る時間を制限し、リラックスできる環境を作ることも大切です。
寝室の温度や湿度を適切に保ち、快適な睡眠環境を整えることで、睡眠の質を向上させることができます。
5. リモートワーク環境での具体的な対策方法

リモートワーク環境でも実践できる、睡眠時無呼吸症候群の予防・改善対策をご紹介します。
これらの対策は、日常生活に取り入れやすく、継続しやすいものを中心に選んでいます。
5-1 食生活の改善
在宅勤務中の食生活の改善は、体重管理と睡眠の質向上に直結します。
まず、規則正しい食事時間を心がけ、夜遅い時間の食事は避けるようにしましょう。
夜食や過度の間食は、体重増加だけでなく、睡眠の質にも悪影響を与えます。特に脂質の多い食事や消化に時間のかかるものは避けましょう。
また、アルコールの摂取にも注意が必要です。
厚生労働省のガイドラインでは、習慣的なアルコール摂取が睡眠時無呼吸症候群を悪化させることが指摘されています。寝酒は一時的に眠りやすくなりますが、深い眠りを妨げ、症状を悪化させる可能性があります。
5-2 作業環境の工夫
在宅勤務の作業環境を工夫することで、運動不足や姿勢の悪化を防ぐことができます。
スタンディングデスクを活用したり、定期的に立ち上がるためのタイマーを設定したりすることが効果的です。
また、椅子の高さやモニターの位置を適切に調整し、正しい姿勢を保つことで、首や肩の筋肉への負担を軽減できます。
パソコンモニターは目線と同じ高さに、椅子は深く腰掛けて足裏が床につくように調整するなど、ご自身の体格に合った環境を整えましょう。これにより、上気道の筋肉の健康維持にもつながります。
5-3 ストレス管理
在宅勤務によるストレスも、睡眠の質に大きく影響します。
定期的な休憩を取り、リラクゼーション法を実践することで、ストレスを軽減できます。
深呼吸や軽いストレッチ、瞑想などが効果的です。アロマを焚いたり、好きな音楽を聴いたりするなど、ご自身に合ったリラックス法を見つけるのも良いでしょう。
また、家族とのコミュニケーションや、同僚とのオンライン交流を積極的に行うことで、社会的なつながりを維持し、精神的な健康を保つことができます。一人で抱え込まず、適度に息抜きをすることも大切です。
6. 早期受診が必要な症状
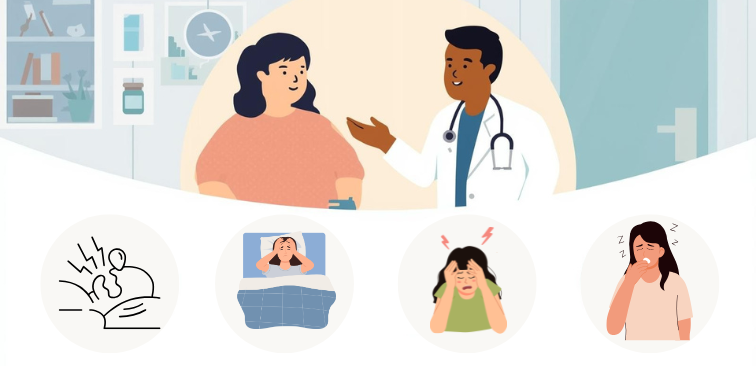
以下のような症状がある場合は、早期の受診をお勧めします。
大きないびきが続く、夜中に息苦しさで目が覚める、朝起きた時の頭痛が頻繁にある、日中の強い眠気が仕事に支障をきたしている、これらの症状に一つでも心当たりがあるなら、早期の受診をお勧めします。
また、家族から「呼吸が止まっている」と指摘された場合や、運転中の居眠りが心配になった場合は、すぐに専門医に相談することが重要です。
睡眠時無呼吸症候群は、適切な治療により症状を大幅に改善できる疾患です。
7. 継続的な管理の重要性

睡眠時無呼吸症候群の治療は、継続的な管理が重要です。
CPAP(持続陽圧呼吸療法)などの治療を受けている方も、定期的な受診とモニタリングが必要です。
また、生活習慣の改善や体重管理についても、医師や看護師からの継続的な継続的なサポートを受けることで、より効果的な結果を得ることができます。
8.おわりに
コロナ禍による在宅勤務の普及は、私たちの生活様式を大きく変化させました。
この変化が睡眠時無呼吸症候群の発症や悪化のリスクを高める可能性があることを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
体重管理、適度な運動、規則正しい生活リズム、ストレス管理を心がけることで、睡眠の質を向上させることができます。
また、気になる症状がある場合は、早めに専門医に相談しましょう。健康な睡眠は、仕事のパフォーマンス向上と生活の質の向上につながります。
あなたの健康な毎日をサポートするためにも、ぜひ本記事でご紹介した対策を実践し、必要であれば早めに専門医にご相談ください。





