咳が止まらない…食べ物の味がしない…それは病気のサインかもしれません
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)
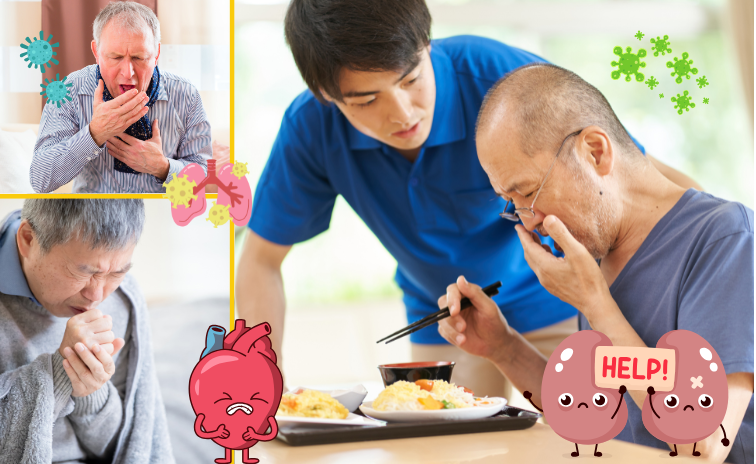
最近、「咳がずっと止まらない」「食べ物の味がしない」と相談に来る高齢の方が増えています。
年齢のせいだろうと病院には行かずに様子を見てしまいがちですが、これらは病気のサインかもしれません。
この記事では、咳が長引くことと、味覚が感じられなくなることが同時に現れる場合に考えられる原因や注意点、受診の目安を解説します。
1. 高齢者の咳と味覚異常は加齢だけが原因ではありません
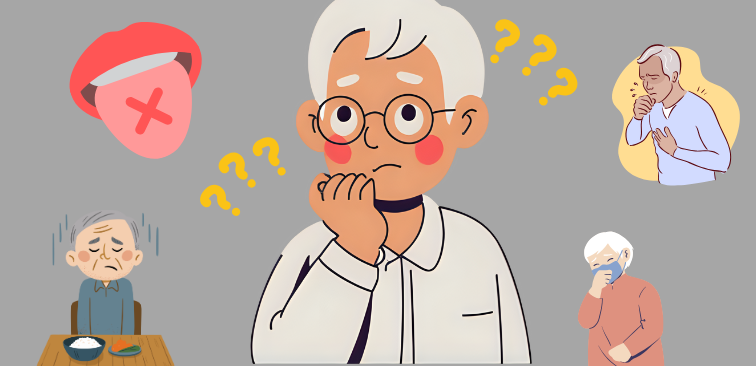
高齢になると味覚が鈍くなったり、喉が渇きやすくなったりしがちですが、「咳が長引く」「味がしない」といった症状がそろって現れる場合、単なる加齢ではなく体の異変を疑う必要があります。
◆「2週間続く咳の原因を探る!あなたの咳はただの風邪?それとも…?」>>
1-1. 年のせいと決めつけず、症状を観察しましょう
人間の味覚や嗅覚(きゅうかく)は加齢に伴って少しずつ低下することがあります。
しかし、急に味がわからなくなるような場合や、咳が数週間以上も続く場合は、年齢のせいだけでは説明できないことがあります。
例えば風邪をひいていないのに咳が続くときは、何らかの疾患が隠れているケースも考えられます。
高齢の方は「昔より味を感じにくい」と感じることはあっても、極端に味覚が失われることはありません。同時に咳が止まらない状態なら、なおさら注意が必要です。
【参考情報】『加齢に関連する注意点』MSDマニュアル
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/multimedia/table/%E5%8A%A0%E9%BD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9?utm_source=chatgpt.com
1-2. 咳と味覚異常が同時に見られるときの背景
咳と味覚(みかく)の異常が同時に起きる背景には、体のさまざまな異常が影響している可能性があります。
例えば気管支炎などの気管の病気では痰(たん)や咳の症状に加え、発熱や食欲不振を伴うことがあり、「食べ物がおいしく感じられない」と表現されることがあります。
またウイルス感染症(例:新型コロナウイルス感染症)でも、咳とともに嗅覚・味覚の異常が起こることが知られています。
こうした症状を「高齢だから仕方ない」と見過ごしてしまうと、肺炎の悪化など重篤な事態を招きかねません。
咳と味覚異常という2つのサインが同時に出ているときは、早めに原因を探ることが大切です。
◆「新型コロナは咳が出る?対処法や後遺症、受診の目安も解説」>>
【参考情報】『急性気管支炎』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/a/a-03.html?utm_source=chatgpt.com
【参考情報】『HER-SYSデータに基づく報告』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000818356.pdf
2. 誤嚥性肺炎の可能性
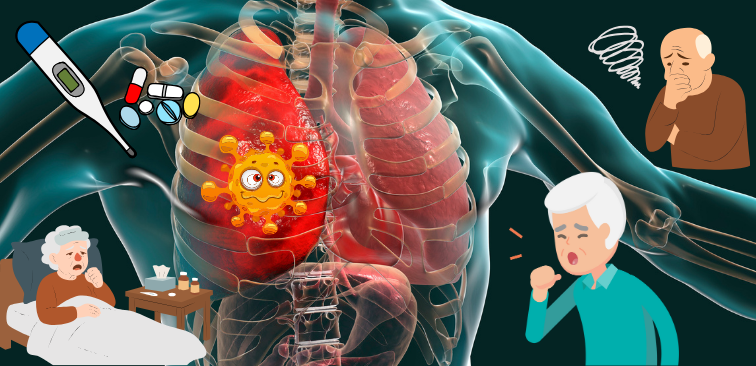
高齢者に特に多いのが誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)です。
誤嚥とは、飲食物や唾液(だえき)を誤って気管に飲み込んでしまうことです。
その結果、肺に細菌が入り炎症が起きると誤嚥性肺炎になります。
高齢の肺炎のうち約7割が誤嚥性肺炎だとも言われており、高齢の方の長引く咳の原因としてまず考えておきたい病気です。
【参考情報】『高齢化に伴い増加する疾患への対応について』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135467.pdf
2-1. 誤嚥性肺炎の症状と特徴
誤嚥性肺炎は、初期には咳が頻繁に出る程度ですが、進行すると痰が絡んできて、微熱程度の発熱や息苦しさが現れる場合があります。
ただし、高齢者の場合は肺炎になっても高い熱が出ないこともあるため注意が必要です。
また、誤嚥性肺炎にかかると、食べ物をうまく飲み込めないため食欲不振になったり体重が減少したりすることもあります。
本人にとって食事が辛くなるだけでなく、栄養が不足して免疫力が低下するとさらに肺炎が悪化しやすくなるため、ご家族の方は、「最近食が細くなった」「食事中によくむせている」といった様子に気付いたら誤嚥性肺炎を疑い、早めに受診させることをおすすめします。
【参考文献】”Aspiration Pneumonia – StatPearls” by NCBI Bookshelf (U.S. National Library of Medicine)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470459/
2-2. 誤嚥性肺炎を防ぐには
普段から食事中の姿勢やお口のケアに気を配ることで、誤嚥性肺炎のリスクを下げられます。
食事のときは背筋を伸ばし、ゆっくり少量ずつ飲み込むようにしましょう。
また、口腔内を清潔に保つため歯磨きやうがいを徹底することで、肺に入る細菌の数を減らすことが期待できます。
ご家族の方も、高齢の方が食事中にあわてず落ち着いて飲み込めるよう見守ってあげると安心です。
もし食事の際に頻繁にむせる場合は、無理せず医療機関で相談し、必要に応じて嚥下(えんげ)機能の検査やリハビリ指導を受けましょう。
【参考情報】『誤嚥性肺炎を防ぎながら、おいしく楽しく食べる毎日を』長野県後期高齢者医療広域連合
https://www.koukikourei-nagano.jp/www/contents/1594357314539/index.html
3. 咳喘息の可能性

咳喘息(せきぜんそく)とは、咳だけが8か月以上続く病気です。
普通の喘息のようなゼーゼーという呼吸音や息苦しさはありませんが、治療せず放っておくと典型的な喘息に移行することもあります。
◆「喘息とはどんな病気か?症状・原因・治療方法を解説!」>>
3-1. 咳喘息の症状と特徴
咳喘息では乾いた咳(痰のあまり出ない咳)が8週間以上にわたり続きます。
夜間から明け方にかけて咳込みやすいのが特徴で、ホコリっぽい場所や冷たい空気を吸ったときに悪化しやすい傾向があります。
熱はなく、風邪薬を飲んでも症状が改善しないときには、まず咳喘息を疑います。
ご家族の方から見ると「夜になると咳がひどくなっている」「季節の変わり目に咳が出ている」といった咳喘息のパターンに気付くかもしれません。
【参考文献】”Cough-Variant Asthma: Causes, Symptoms & Treatment” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25200-cough-variant-asthma
3-2. 咳喘息かなと思ったら
咳喘息が疑われる場合、できるだけ早めに呼吸器内科を受診して相談しましょう。
咳喘息自体は気管支拡張薬や吸入ステロイド薬で治療することで、多くは改善します。
ただし前述のように、放置すると気管支喘息(ぜん息)に発展するケースもあり、ぜん息になると治療が難しく、呼吸困難などの重篤な発作があるため、高齢の方にとっては大きな負担となります。
そうなる前に、長引く咳は「ただの風邪ではないかも」と考えて専門医に診てもらうことが大切です。
【参考情報】『咳喘息』日本内科学会
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/10/109_2116/_pdf
4. 神経系の病気やウイルス感染の可能性

味覚や嗅覚の異常がある場合、神経系の病気やウイルス感染の後遺症などが関与していることも考えられます。
例えば、高齢者ではパーキンソン病などの神経疾患で嗅覚(におい)の低下が現れることがあります。
また、近年話題になった新型コロナウイルス感染症でも、嗅覚や味覚の異常が症状として出ることが知られています。
4-1. 神経疾患による味覚・嗅覚の変化
脳や神経の病気によって味覚や嗅覚が変化することがあります。
例えば脳梗塞の後遺症で舌や喉の感覚が鈍くなり、食べ物の味を感じづらくなることがあげられます。その結果、食事量が減ってしまい体調を崩すケースもあります。
また、パーキンソン病やアルツハイマー型認知症の初期症状として「においが分かりにくくなる」ことが指摘されています。
においを感じにくいと食欲が低下し、「味がしない」と感じる原因にもなります。
咳はこれらの神経疾患の主症状ではありませんが、飲み込みの反射が弱まることで誤嚥を起こしやすくなり、二次的に咳込むことが増える場合があります(誤嚥性肺炎のリスクが高まります)。
【参考情報】『脳血管障害による嚥下障害への対応』J-Stage
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlp/52/3/52_3_197/_pdf
【参考情報】『“におい”の情報はQOL維持に欠かせない』日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
https://www.jibika.or.jp/owned/healthy-aging/smell.html
4-2. ウイルス感染後の味覚障害
風邪やインフルエンザなどの感染症の後に、一時的に味覚や嗅覚が鈍くなることがあります。
特に新型コロナに感染した後、「味やにおいがしない」という後遺症が長引く場合もあるため、高齢者が過去に感染し、その影響が残っている場合も考えられます。
この場合、咳も感染後しばらく残ることがあるため、「咳が続く+味がしない」という状態になることがあります。
ウイルス後遺症による味覚・嗅覚異常は時間の経過とともに回復することも多いですが、長期間改善しない場合は専門医に相談してみてください。
【参考情報】『嗅覚・味覚障害と新型コロナウイルス感染症について』日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
https://www.jibika.or.jp/modules/news_citizens_covid19/index.php?content_id=8
5. 口腔乾燥(ドライマウス)による影響である可能性
による影響である可能性.png)
高齢者ではお口の中が乾燥するドライマウスの状態も珍しくありません。
ドライマウスとは、唾液の分泌が減ったり、薬の副作用や口呼吸の習慣などで口が渇きやすくなったりする状態のことです。
実はこのドライマウスも、咳と味覚異常に関係することがあります。
【参考情報】『高齢者のQOLを低下させるドライマウスへの対応』長寿科学振興財団
https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/gyoseki/pdf/h31-5-3-7.pdf?utm_source=chatgpt.com
5-1. ドライマウスだと咳が出やすい?
唾液には口の中を潤し、細菌や異物を洗い流す働きがあります。
しかし高齢者は唾液の分泌が減りやすく、その結果として喉や気管が乾燥し、刺激に敏感になって咳が出やすくなります。
特に夜間、寝ている間に口呼吸で喉が乾燥すると、朝方に「カラ咳」が出る原因になることもあります。
また唾液には粘膜を守る作用があるため、唾液が少なくなると喉がいがらっぽくなり、慢性的な咳の一因となることがあります。
5-2. ドライマウスだと味が分かりにくい?
唾液は味を感じる上でも重要です。
食べ物が唾液に溶けることで舌の味蕾(みらい、味覚を感じる細胞)が刺激され味を感じます。
そのため、口が乾いていると味蕾がうまく働かず、ドライマウスの方は味を薄く感じたり、味覚が鈍くなったりします。
さらに唾液には抗菌作用もあるため、虫歯ができやすくなったりといった問題も生じます。
ドライマウスの対策としては、こまめな水分補給や保湿ケア(のど飴をなめる、加湿器を使う等)が有効です。
口腔乾燥が強い場合は、歯科や耳鼻咽喉科で相談すると、人工唾液の処方やマウスピースなど適切な処置を受けられることがあります。
【参考情報】『航空乾燥症(ドライマウス)』北海道薬剤師会
https://www.doyaku.or.jp/guidance/data/H22-11.pdf
6. まとめ
高齢者の「咳が止まらない」「味がしない」という症状は、加齢だけでなく誤嚥性肺炎や咳喘息などの病気のサインかもしれません。
特に長引く咳や味覚異常は放置せず、早めに医療機関で相談しましょう。
呼吸器内科、耳鼻咽喉科、神経内科など症状に応じた専門医の診察が必要になる場合もありますが、まずは地域のクリニックで気軽にご相談ください。
大切なご家族の健康を守るため、早期受診が何よりも重要です。





