子どもの咳が続く…それは気管支喘息?受診の目安と家庭での対応
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)
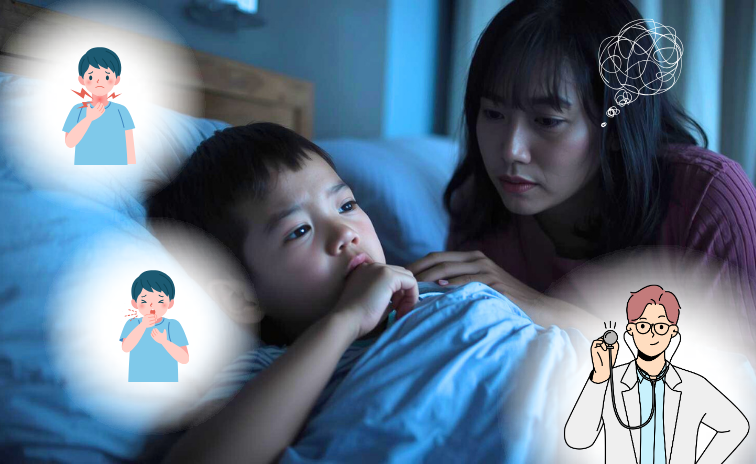
大切なお子さんの咳が続くと、ご家族も心配になりますよね。
子どもの気管支喘息(小児喘息)とは、空気の通り道である気道に慢性的な炎症が起こり、気道が狭くなることで咳や呼吸のしづらさなどの症状が現れる病気です。
また成長とともに症状が落ち着く子もいますが、約3割は大人になっても喘息が持続するともいわれます。
長いスパンで経過を見る必要がある病気のため、早期発見・早期治療が重要です。
1.子どもの喘息の初期症状パターン

小児喘息の初期には、大人とは違ったパターンで症状が現れることがあります。
「風邪は治ったのに、子どもの咳だけが長引いている」「運動をした後や季節の変わり目に子どもが決まって咳き込む」など、思い当たるケースはないでしょうか。
ここでは子どもに見られやすい喘息の初期症状パターンを二つ紹介します。
1-1.風邪の後に咳だけ長引く場合
子どもが風邪をひいた後、「熱や鼻水は治まったのに咳だけが何週間も続いている」という場合は要注意です。
このように風邪の症状が治った後も咳がしつこく残るのは、小児喘息の初期によく見られるパターンの一つです。
特に夜間や明け方になるとコンコンと咳き込みやすく、昼間は比較的元気なので見逃されやすい傾向があります。
咳が2週間以上続くなら、喘息の可能性があります。
特に、喘鳴や呼吸困難がなく咳だけが続く「咳喘息」は風邪をきっかけに発症しやすく、夜も眠れないほど咳き込むこともあります。
咳が長引く場合は、喘息を疑う重要なサインです。
「ただの風邪の後の咳」と油断せず、咳が長引く場合は早めに医療機関を受診する目安と考えてください。
◆「2週間続く咳の原因を探る!あなたの咳はただの風邪?それとも…?」>>
◆「咳を止める方法は?しつこい咳、長引く咳から疑われる病気と受診の目安を紹介」>>
1-2.運動後や季節の変わり目に咳き込みやすい場合
運動後に「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と咳き込むのも、喘息のサインかもしれません。
これは「運動誘発性喘息」と呼ばれ、運動の刺激で一時的に気道が狭くなる状態です。
特に冷たく乾いた空気を吸い込む冬場の運動などで起こりやすくなります。
また季節の変わり目(気温や湿度、気圧が大きく変化する時期)にも注意が必要です。台風の接近時や季節の交替期に咳込む子は、気道が過敏になっている可能性があります。
季節の変わり目や運動後に咳き込む場合、喘息の可能性を考えて環境を整えたり事前に予防策を取ったりすることが大切です。
医師の指示のもとで運動前に発作を予防する吸入薬を使用したり、室内の温度・湿度を調整したり、マスクを着用したりすることが有効です。
こうした工夫で咳発作を減らせる場合があるため、心当たりがあれば専門医に相談しましょう。
【参考情報】『運動時のポイント| 小児ぜん息基礎知識』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/kodomonozensoku/undo.html
【参考文献】“Exercise-induced asthma ‒ Symptoms & causes” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/exercise-induced-asthma/symptoms-causes/syc-20372300
2.小児喘息に特徴的な症状と見逃しやすいサイン

小児喘息のサインは、咳やゼーゼー音だけではありません。親が見逃しやすい子どもの変化にも注意しましょう。
● 喘鳴(ぜいめい)
息を吐くときの「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音は喘息の代表的な症状です。ただし、子どもは気道が細いため、音が聞こえにくかったり、逆に痰が絡んだ音を喘鳴と間違えたりすることもあります。「息を吐くのに苦しそう」といった様子も観察しましょう。
● 夜間の悪化
昼間は元気でも、夜中から明け方にかけて咳き込むのは喘息の典型的なパターンです。日中の様子だけで「大丈夫」と判断せず、夜間の咳も医師に伝えましょう。
● 不機嫌・落ち着きのなさ
小さな子どもは「息が苦しい」と上手く言えません。代わりに、ぐずったり、不機嫌になったりして不調を訴えることがあります。普段と違う様子が続くなら、息苦しさを疑ってみることも大切です。
● アレルギー体質や家族歴
親や兄弟に喘息の人がいる、または子ども自身がアトピー性皮膚炎や食物アレルギーなどを持っている場合、喘息を発症しやすい傾向があります。
また、乳幼児は他の感染症でも喘息に似た症状が出ることがあります。自己判断せず、気になるサインがあれば専門医に相談することが重要です。
【参考情報】『Q3. 夜間や早朝にせきが出ます。』日本呼吸器学会 呼吸器Q&A
https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q03.html
3.喘息の原因と発作の引き金になるもの

ここでは小児喘息の主な原因となるアレルギーと、症状を誘発・悪化させる要因について説明します。
3-1.アレルギーが主な原因
小児喘息のほとんどは、特定の物質(アレルゲン)に対するアレルギー反応が気道で起こることが原因です。代表的なアレルゲンには以下のようなものがあります。
・ハウスダスト(ホコリ)やダニ
・カビの胞子
・ペットの毛やフケ
・花粉(スギなど)
・食物(卵、牛乳など)
これらが原因かどうかは、血液検査で特定できます。
原因物質が判明すれば、こまめな掃除や寝具の洗濯、ペットとの接し方の工夫など、生活環境を整えることで発作の予防につながります。
【参考情報】『小児のぜん息/Q&A』日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=2
3-2.喘息症状を誘発・悪化させる刺激
アレルギーだけでなく、以下のような身近な刺激も発作の引き金になります。
・タバコの煙、強いにおい
・排気ガス、黄砂、PM2.5
・台風や季節の変わり目の寒暖差・気圧の変化
・冷たく乾燥した空気、エアコンの風
・激しい運動
・ストレスや睡眠不足
特に風邪などの感染症は、発作の大きな誘因となります。
発作を繰り返すと気道の炎症が慢性化し、さらに過敏になる悪循環に陥るため注意が必要です。
発作予防の基本は、これらの悪化因子を避けることです。
禁煙や換気、加湿器の使用、手洗いやマスクによる風邪予防、ストレス管理など、子どもの体調と生活環境に気を配りましょう。
4.早めの受診と小児喘息の治療・フォロー体制

4-1.受診の目安と救急のサイン
「もしかして喘息かも?」と感じたら、早めに医療機関を受診することが肝心です。
特に子どもの場合は症状を自分で正確に伝えられないため、保護者が判断してあげる必要があります。
これまで述べたような症状がみられ、日常生活に支障が出ているようなら、一度小児科や呼吸器の専門医に相談しましょう。また明らかな発作症状がある場合は迷わず受診してください。
例えば「遊べない・話せないほど息苦しそう」「顔色が悪くボーッとしている」「強いゼーゼー音があり、呼吸するたび肋骨の間がへこむ(陥没呼吸:かんぼつこきゅう)」といった様子が見られるときは、重篤な喘息発作のサインです。
このような場合は夜間でも救急受診すべきレベルですので、ためらわず医療機関を受診してください。
【参考文献】“Childhood asthma – Symptoms & causes” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/childhood-asthma/symptoms-causes/syc-20351507
4-2.診断の流れ(問診・診察・検査)
小児喘息が疑われる場合、医療機関では問診や診察、必要に応じて各種検査を行い総合的に診断します。
小さな子どもは正確な呼吸機能検査が難しいため、症状の経過やアレルギー歴などの詳しい問診が診断の決め手となります。
保護者の方は、お子さんの咳が「いつから」「どんな時に」出るのか、夜間はどうか、家族に喘息持ちがいるか、などを具体的に医師に伝えてください。
また血液検査でアレルギーの有無や原因アレルゲンを調べることもあります。必要ならば専門的な呼吸器検査(胸部X線、呼吸機能検査など)を行うこともあります。
【参考情報】『ぜん息』国立成育医療研究センター
https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/allergy/asthma.html
4-3.治療の基本(コントローラーとリリーバー)
診断がついたら、早速喘息の治療を開始します。
子どもの喘息治療では、発作を予防するために毎日使用する長期管理薬(コントローラー)と、発作が起きたときに使用する発作治療薬(リリーバー)を併用するのが基本です。
長期管理薬の中心となるのは「吸入ステロイド薬」です。
これは気道の炎症を直接抑える働きがあり、喘息治療で最も基本的で重要な薬です。全身への影響が少ないよう工夫されており、適切に使用すれば安全に長期間治療を続けることができます。
これを毎日継続して吸入することで、発作の頻度と重症度を大幅に減らすことができます。
一方、発作治療薬としては気管支拡張薬(吸入または内服)が用いられます。
発作時に狭くなった気管支を広げて咳や喘鳴を緩和する薬で、即効性があります。
注意点として、気管支拡張薬はあくまで一時的に症状を和らげるだけで、炎症そのものを治療する効果はありません。
発作治療薬だけでは根本的な炎症は治まりません。
毎日使う長期管理薬で気道の炎症を普段から抑え、発作そのものを起こさないようにすることが現代の喘息治療の基本です。
医師の指示を守って治療薬を続ければ、発作なく過ごせる状態を維持でき、健康な子と同じように運動や遊びもできるようになります。
4-4.経過観察と自己管理(症状日誌)
治療開始後は、定期的に経過観察と治療内容の調整を行います。
お子さんの症状日誌(咳や発作の頻度・程度、ピークフローメーター(息を思い切り吐いたときの速さを測る器具)の値など)をつけ、受診時に医師と共有すると良いでしょう。そうすることで、現在の治療が適切か、薬を増減すべきか、重症度はどの程度か、といった判断がしやすくなります。
喘息は長期的な管理が必要な病気です。子どもの頃の治療が将来の状態にも影響するため、主治医とよく相談し、根気よく治療を続けることが何より大切です。
5.まとめ
子どもの長引く咳や「ゼーゼー」という呼吸音は、気管支喘息のサインかもしれません。
「風邪の後に咳だけ続く」「運動後や夜間に咳き込む」といった場合は注意が必要です。
小児喘息の多くはアレルギーが原因のため、症状に気づいたら早めに医療機関を受診しましょう。
吸入薬などで気道の炎症を抑える治療を継続すれば、発作を防ぎ元気に過ごせます。
お子さんのサインを見逃さず、適切な対応を心がけましょう。お子さんが健やかに毎日を送れるよう、ご家族と医療者がチームとなって、喘息と上手に付き合っていきましょう。





