喘息は遺伝する?
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)

喘息が遺伝するかと気にされている方は多いのではないでしょうか。遺伝する病気には、単一遺伝子疾患と多因子疾患の2種類があります。
喘息は多因子疾患のひとつで、遺伝子の影響だけでなく環境要因も発症に関わります。親が喘息であっても、必ずお子さまが発症するわけではありません。
しかし、アレルギー体質は遺伝する可能性があるため、喘息以外のアレルギー疾患を発症することはあります。
この記事では、喘息と遺伝の関係性についてご説明いたします。適切な環境整備と早期治療により、喘息があっても健康的な生活を送りましょう。
1. 遺伝する病気と仕組み
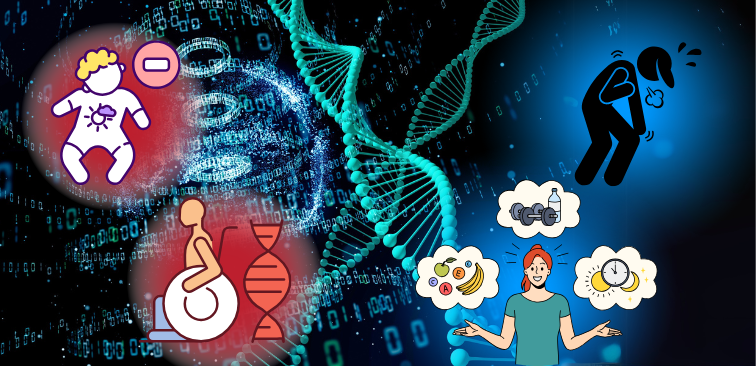
遺伝する可能性のある病気について、気になっている方は多いのではないでしょうか。
遺伝性疾患には大きく分けて2つの種類があり、その仕組みもさまざまです。ここからは、遺伝する病気の主な2種類のタイプについてご説明いたしましょう。
1-1. 単一遺伝子疾患
単一遺伝子疾患とは、特定の遺伝子の変異によって引き起こされる疾患のことです。このタイプの病気は、変異した遺伝子を持っているだけで発症する可能性が非常に高くなります。
以下に、単一遺伝子疾患の代表的な例をご説明いたします。
・フェニルケトン尿症
フェニルケトン尿症は、体内でフェニルアラニンというアミノ酸を分解する酵素の遺伝子に異常があることで発症します。
この病気を持って生まれた赤ちゃんは、適切な食事療法を行わなければ、知能の発達に影響を及ぼす可能性があります。
しかし、早期に診断され、適切な食事管理を続けることで、健康的な生活を送ることが可能です。
・筋緊張性ジストロフィー
筋緊張性ジストロフィーは、筋肉の機能を制御する遺伝子に異常が生じることで発症し、徐々に筋力が低下していく疾患です。
進行性の疾患であり、全身のさまざまな筋肉に影響を及ぼすため、日常生活にも大きな支障をきたすことがあります。
・ハンチントン病
ハンチントン病は常染色体優性遺伝の単一遺伝子疾患です。脳の線条体に強い変性と細胞死を引き起こし、筋肉の不随意運動を生じさせます。
・血友病
血友病はX連鎖性劣性遺伝の単一遺伝子疾患の代表例です。血液凝固因子の遺伝子に変異があることで発症し、主に男性に現れます。
血液が正常に凝固しないため、出血が止まりにくくなります。
・ウィルソン病
ウィルソン病は常染色体劣性遺伝の単一遺伝子疾患です。銅の代謝に関わる遺伝子の変異によって引き起こされ、体内に銅が蓄積することで肝臓や脳に障害を及ぼします。
・マルファン症候群
マルファン症候群は常染色体優性遺伝の単一遺伝子疾患で、結合組織の形成に関わる遺伝子の変異が原因です。長い手足や指、心臓弁の異常、眼の水晶体の異常などの特徴的な症状を示します。
これらの疾患は、親から子へと高い確率で遺伝するため、遺伝子検査や出生前診断が重要です。
医学の進歩により、早期発見や治療法の開発が進んでおり、患者さんの生活の質を向上させるための取り組みが続けられています。
【参照文献】日本医学会連合『ヒトの遺伝性疾患』
https://www.jmsf.or.jp/genome/3-1.php
【参考文献】”Phenylketonuria (PKU)” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/phenylketonuria/symptoms-causes/syc-20376302
【参考文献】”Myotonic Dystrophy” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24516-myotonic-dystrophy-dm
【参考文献】”Marfan syndrome” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/marfan-syndrome/symptoms-causes/syc-20350782
1-2. 多因子疾患
多因子疾患は、単一遺伝子疾患とは異なり、複数の遺伝子と環境要因が組み合わさって発症する病気です。
喘息は多因子疾患のひとつとして考えられています。
多因子疾患の特徴は、遺伝子だけでなく、生活習慣や環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症することです。
そのため、親が持っている遺伝子をお子さまが受け継いだとしても、必ずしもその病気を発症するわけではありません。
たとえば、喘息に関連する遺伝子を親から受け継いだお子さまがいたとしましょう。このお子さまが、必ずしも喘息を発症するとは限らないということです。
喘息の発症には、生活環境やアレルゲンへの曝露、ストレスといったさまざまな要因が影響を及ぼします
一卵性双生児の研究を見ても、多因子疾患の特徴がよくわかります。
一卵性双生児は全く同じ遺伝子を持っていますが、多因子疾患の場合、片方の方が発症しても、もう一方の方は発症しないことがあります。
この違いは、成長過程での環境や経験の差によるものだと考えられています。
繰り返しになりますが、喘息は喘息に関連する遺伝子を持っているだけでは発症するとは限らないのです。
むしろ、遺伝的な素因を持っていたとしても、適切な環境管理や生活習慣の改善によって、発症を予防したり、症状をコントロールすることが可能です。
このように、多因子疾患である喘息は、遺伝だけでなく環境要因も大きく関わる病気です。
そのため、喘息を管理し予防するには、遺伝的な背景を理解しながらも、生活環境を整え、適切な治療を行うことが重要になります。
2. アレルギーと遺伝の関わり
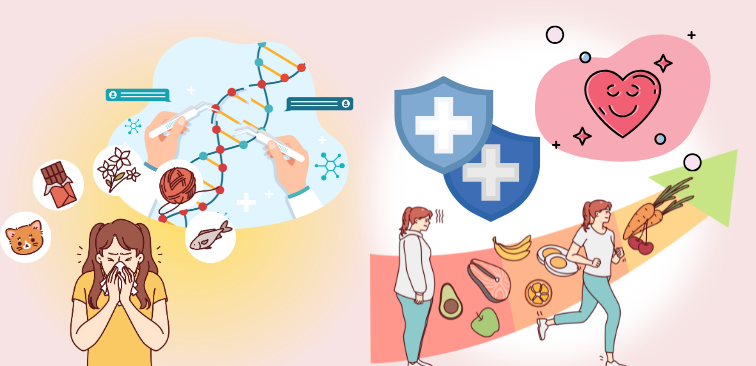
アレルギーと遺伝の関係については、多くの方が興味を持たれているのではないでしょうか。
実際、アレルギー疾患と遺伝には深い関わりがあります。
ここからは、アレルギー反応の仕組みと遺伝との関連性についてご説明しましょう。
まず、アレルギー反応について理解することが大切です。
私たちのからだには、外敵から身を守るための「免疫」というシステムが備わっています。免疫システムには通常、細菌やウイルスなどの有害な物質を識別し、排除する役割があります。
しかし、アレルギー体質の方の場合は、本来は無害なはずの物質(アレルゲン)に対しても免疫システムが過剰に反応してしまいます。
その結果、くしゃみや鼻水、皮膚の発疹、喘息の症状など、さまざまなアレルギー反応が引き起こされるのです。
アレルギーが原因の病気には、さまざまな種類のものがあります。
たとえば、花粉症、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息などが代表的です。
これらの疾患は、それぞれ異なる症状がありますが、根本的な原因はアレルギー反応にあります。
ここで重要なのは、アレルギー体質そのものは遺伝する可能性があるということです。つまり、親がアレルギー体質であれば、お子さまも同じようなアレルギー体質を受け継ぐ可能性が高くなります。
一方で、注意しなければならないのは、特定のアレルギー疾患がそのまま遺伝するわけではないということです。
たとえば、親が喘息だからといって、お子さまも必ず喘息になるわけでありません。しかし、お子さまは親とは異なるアレルギー性疾患を発症する可能性があるといえます。
具体的には、喘息の親を持つお子さまが、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーを発症するケースがあります。
また、逆に、アトピー性皮膚炎の親を持つお子さまが、喘息を発症することもあります。
これは、アレルギー体質という大きな枠組みは遺伝するものの、具体的にどの疾患として現れるかは、生活環境や個人の体質によって違いが出るためです。
さらに、最近の研究では、アレルギー疾患の発症に関わる遺伝子がいくつか特定されています。
たとえば、喘息やアトピー性皮膚炎の発症リスクを高める遺伝子変異が見つかっています。これらの遺伝子は、免疫システムの調整や、皮膚のバリア機能に関わっているものが多いようです。
ただし、これらの遺伝子を持っているからといって、必ずアレルギー疾患を発症するわけではありません。
遺伝子は発症のリスクを高めるものの、実際の発症には環境要因が大きく関わってくるのです。
また、興味深いことに、アレルギー疾患は「アレルギーマーチ」と呼ばれる現象を示すことがあります。
これは、年齢とともにアレルギー症状が変化していく様子を表現したものです。
たとえば、乳児期はアトピー性皮膚炎になり、幼児期に食物アレルギー、学童期に喘息、成人期に花粉症へと移行していくようなケースがあります。
このように、アレルギーと遺伝の関係は非常に複雑で、まだ完全には解明されていません。
しかし、アレルギー体質が遺伝する可能性があることを知っておくことは、予防や早期対応の観点から非常に重要です。
もし、ご家族にアレルギー疾患を持つ方がいる場合、お子さまもアレルギーを発症するリスクが高くなる可能性があります。しかし、それを悲観的に捉える必要はありません。
むしろ、この知識を活かし、早い段階から適切な環境を整えたり、生活習慣を見直したりすることで、アレルギーの発症を防いだり、症状を和らげたりすることができます。
予防や対策を意識することで、お子さまがより健やかに成長できる環境をつくることができるのです。
【参照文献】環境再生保全機構 『Q4.ぜん息は遺伝しますか。』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/50/feature/feature04.html
3. 環境と遺伝の関わり

環境と遺伝の関係は、喘息をはじめとするアレルギー疾患の発症に深く関わっています。この2つの要因がどのように影響し合うのかを理解することは、予防や管理において非常に重要です。
ここからは、環境と遺伝の複雑な関係についてみていきましょう。
まず知っておきたいのは、前述どおり、喘息になりやすい体質、つまり遺伝的な素因を持っていたとしても、必ずしも喘息を発症するわけではないということです。
実際、全く同じ遺伝子を持つ一卵性双生児であっても、ひとりが喘息を発症し、もうひとりは発症しないケースがあります。
この違いは、環境要因が大きな影響を与えていることを示しています。
喘息の発症リスクを高める環境要因には、大気汚染や家庭内のダニ・カビ、ペットの毛、タバコの煙、ウイルス感染などが挙げられます。
これらが気道を刺激し、喘息の発症や悪化を引き起こすのです。
しかし、環境を適切に整えることで、たとえ喘息になりやすい体質を持っていたとしても、発症を防いだり、症状を抑えたりすることが可能です。
つまり、遺伝的な素因があるからといって必ず発症するわけではなく、環境次第で喘息と上手に付き合っていくことができるのです。
では、具体的にどのような環境整備が効果的なのでしょうか。以下に、いくつかの重要なポイントをご紹介しましょう。
・こまめな掃除
ダニやホコリは喘息の大敵です。とくに、寝具やじゅうたん、ソファーなどは要注意です。
週に1〜2回は掃除機をかけ、寝具は定期的に日光消毒を行うのが理想です。また、ダニ対策用のカバーを使用するのもいいでしょう。
・適切な湿度管理
カビの発生を防ぐために、室内の湿度管理が重要です。
除湿器を使用したり、こまめに換気を行ったりすることで、適切な湿度(40〜60%程度)を保ちましょう。
とくに、梅雨時期や結露しやすい冬場は注意が必要です。
・ペットの管理
ペットのフケや毛も喘息の原因となることがあります。可能であれば、ペットは屋外で飼育するか、少なくとも寝室には入れないようにしましょう。
また、定期的なブラッシングやシャンプーも効果的です。
・禁煙
タバコの煙は、喘息の症状を悪化させる大きな要因のひとつです。
喫煙者のご本人はもちろん、ご家族や周囲の方の禁煙も重要です。とくに、お子さまがいる家庭では、徹底した禁煙が求められます。
・アレルゲンの特定と回避
ご自分にとってのアレルゲン(アレルギーの原因物質)を特定し、できるだけ接触を避けることが大切です。
たとえば、花粉症の方であれば、花粉の飛散時期には外出を控えたり、マスクを着用したりするなどの対策が有効です。
・適度な運動
適度な運動は、肺機能を向上させ、喘息のコントロールに役立ちます。ただし、運動誘発性喘息がある方は、医師と相談の上、適切な運動方法を選択することが重要です。
・ストレス管理
ストレスは喘息の症状を悪化させることがあります。瞑想やヨガ、深呼吸法など、ご自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。
・予防接種
インフルエンザなどのウイルス感染は、喘息の症状を悪化させる可能性があります。医師と相談の上、必要な予防接種を受けることを検討しましょう。
以上のような環境整備は、喘息の予防や症状のコントロールに非常に効果的です。
しかし、すべての対策を一度に実行するのは難しいかもしれません。まずは、ご自分やご家族の状況に合わせて、できることから少しずつ始めていくことが大切です。
また、これらの環境対策は、喘息だけでなく、ほかのアレルギー疾患の予防や症状の緩和にも効果があります。
たとえば、アトピー性皮膚炎や花粉症の方にとっても、清潔な環境を保つことは非常に重要です。
さらに、近年の研究では、腸内細菌叢(腸内フローラ)と喘息やアレルギーの関連性が注目されています。
とくに、生後間もない時期の腸内環境が、その後のアレルギー疾患の発症リスクに影響を及ぼす可能性があることが明らかになってきました。
このことから、バランスの取れた食事を心がけることや、必要に応じてプロバイオティクスを取り入れることが、アレルギー予防の観点から重要であると考えられています。
腸内環境を整えることで、免疫機能の発達を助け、アレルギー疾患のリスクを低くできる可能性があるのです。
環境と遺伝の相互作用を理解することで、喘息やアレルギーとより上手に向き合うことができます。
たとえ遺伝的な素因を持っていたとしても、それが必ず発症につながるわけではありません。
適切な環境管理と生活習慣の改善によって、症状をコントロールしながら、健康的な生活を送ることは十分に可能です。
【参照文献】筑波大学・科学技術振興機構『腸内細菌のバランスの乱れが、喘息を悪化させるメカニズムを解明—新しい発想のアレルギー治療へ—』
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20140116/
4. おわりに
喘息は遺伝的要素と環境要因の相互作用で発症します。遺伝因子があっても、必ずしも発症するわけではありません。
適切な対策で発症リスクを下げたり、症状をコントロールしたりできます。
早期の適切な治療により、健康な方と変わらない生活を送ることが可能です。現代の医療技術の進歩により、効果的な薬剤が開発され、多くの方が症状をうまくコントロールしています。
定期的な通院と医師の指示に従った服薬を継続することを欠かさないようにしましょう。自己判断で治療を中断すると、症状が再燃する可能性があります。
患者さん自身の積極的な参加も大切です。日々の症状や薬の使用状況の記録、ピークフローメーターでの肺機能チェックにより、自分の状態を把握し、医師とより良いコミュニケーションを取ることができます。
喘息になったとしても、決して悲観する必要はありません。
適切な知識と対策があれば、喘息は十分にコントロール可能です。必要に応じて医療機関に相談しながら、健康的な生活を送りましょう。





