肺血栓塞栓症について解説
(横浜日ノ出町呼吸器内科・内科クリニック院長)

肺血栓塞栓症は、血栓が肺の血管を塞ぐことで起こる深刻な疾患です。
別名「エコノミークラス症候群」とも呼ばれ、長時間の同じ姿勢による血流の停滞が原因となることがあります。
この記事では、肺血栓塞栓症の特徴、症状、診断方法、治療法、予防法についてご説明いたします。
1. 肺血栓塞栓症とは?

肺血栓塞栓症は、血液中に形成された血栓(血のかたまり)が肺の血管に流れ込み、血管を塞ぐことで発症する疾患です。
肺血栓塞栓症では、血液中の酸素の取り込みが不十分になり、全身に十分な酸素を含む血液を送り出せなくなるため生命に危険が及ぶ可能性があります。
肺血栓塞栓症の主な原因は、下肢(脚・足)の血管にできた血栓です。下肢の血管に血栓ができた状態を下肢深部静脈血栓症と呼びます。
下肢の血栓が肺の血管に流れ込むことで、肺血栓塞栓症を発症します。
血栓ができやすい方の特徴として、以下のようなものがあります。
・水分を十分に摂れていない方(とくに高齢者の方)
・肥満や糖尿病などにより、血液の流れが悪くなっている方
・高血圧の方
・車の運転や飛行機の搭乗などで長時間座っている方
・手術のあとや何らかの病気で、長期間下肢を十分に動かせていない方
・なんらかの病気や薬により、血液が固まりやすくなっている方
・遺伝的に血栓ができやすい体質の方
また、経口避妊薬(ピル)を服用している方も、場合によっては血栓発症のリスクが高くなることがあるため注意が必要です。
なお、肺血栓塞栓症は、「エコノミークラス症候群」という別名でも知られています。
これは、飛行機の狭い座席に長時間座った状態でいることが原因で発症することが多いためです。
一方で、「エコノミークラス症候群」という名称は誤解を招く可能性があります。
なぜなら、実際には飛行機への乗車時に限らず、長時間同じ姿勢を続けることで発症リスクが高まるためです。
たとえば、長時間のデスクワークや、長距離ドライブ、入院中の安静など、さまざまな状況で肺血栓塞栓症は発症する可能性があります。
そのため、飛行機に乗る以外での日常生活においても注意が必要だといえるでしょう。
このように、肺血栓塞栓症は、さまざまな場面で突然発症し、急速に症状が悪化する可能性があるため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。
次の章では、肺血栓塞栓症の症状についてご説明いたしましょう。
【参考文献】”Pulmonary embolism” by MayoClinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-embolism/symptoms-causes/syc-20354647
2. 症状

肺血栓塞栓症の症状は、血栓の大きさや位置、患者さんの全身状態によって異なります。主な症状には以下のようなものがあります。
・急な息切れ
・胸の痛み
・咳
これらの症状は突然現れることが多く、重症度によっては生命に危険が及ぶ可能性があります。
息切れは、肺血栓塞栓症の最も一般的な症状のひとつです。
通常の活動で急に息苦しくなったり、息が荒くなったりする場合は注意が必要です。
突然の息切れは、血栓によって肺への血流が妨げられ、十分な酸素が体内に取り込めないことが原因です。
胸の痛みは、多くの場合、鋭い痛みや圧迫感として感じられます。この状態の痛みは、呼吸をするたびに悪化することが知られています。
また、胸の痛みは、心臓発作の症状と似ていることがあり、いずれにしても、すぐに医療機関を受診することが重要です。
咳は、時に血痰を伴うことがあります。これは、肺の組織が損傷を受けていることを示す可能性があるためです。
塞がった肺の血管の範囲が小さい場合、症状がほとんど現れないこともあります。
一方で、塞がった血管の範囲が大きい場合は、非常に危険な状態となり、以下のような重篤な症状が現れる可能性があります。
・意識の喪失
・心停止
・低血圧
・めまい
・発汗
また、肺血栓塞栓症の早期発見のためには、下記のような下肢の症状にも注意を払う必要があります。
・太ももからふくらはぎにかけての赤み
・腫れ
・痛み
・ふくらはぎの太さの左右差
これらの症状は、下肢に血栓ができたときに発生する症状で、肺血栓塞栓症に至る前の段階である可能性を考える必要があります。
このような症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
さらに、下肢の症状が現れたあとに胸の痛みなどが生じた場合は、肺血栓塞栓症の可能性が高いため、直ちに救急車を呼ぶなどして緊急の医療処置を受ける必要があります。
肺血栓塞栓症の症状は、ほかの疾患の症状と似ていることがあるため、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。
とくに、リスク因子を持つ方や、長時間の同じ姿勢を続けた後に上記のような症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
次の章では、肺血栓塞栓症の診断方法や検査についてご説明いたします。
【参考文献】”Pulmonary Embolism” by JOHNS HOPKINS MEDICINE
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pulmonary-embolism
3. 診断・検査
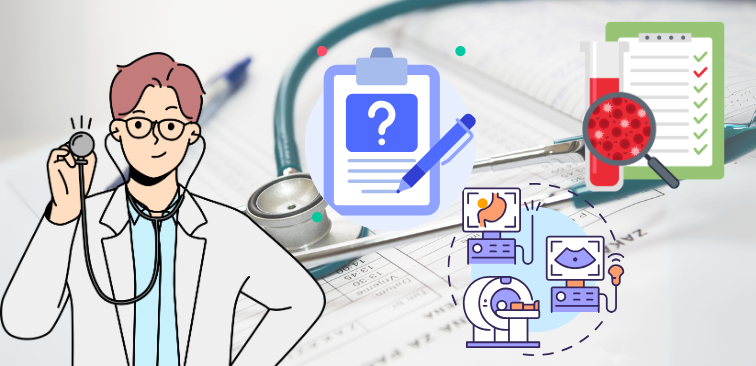
肺血栓塞栓症の診断は、症状や身体所見、さまざまな検査結果を総合的に判断して行われます。以下に、診断の方法と主な検査についてご説明いたします。
初期評価
医療機関を受診すると、まず医師が以下の初期評価を行います。
・症状の聴取(問診)
バイタルサインのチェック(血圧、脈拍、呼吸数、体温など)
血中酸素飽和度(SpO2)の測定
身体診察(聴診器を用いた心音や呼吸音の確認、下肢の腫れや痛みのチェックなど)
・血液検査
血液検査では、以下のような項目をチェックします。
・D-ダイマー:血栓が溶解されたときに増加するタンパク質
・血液ガス分析:動脈血中の酸素や二酸化炭素の濃度を測定
・心筋トロポニン:心筋障害の有無を確認
・BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド):心不全の程度を評価
・画像検査
肺血栓塞栓症の診断で最も重要とされている検査は、造影CT検査です。
造影CTは、造影剤を静脈から注入し、肺動脈の血流を詳細に観察する検査方法です。血栓がある部分には造影剤が流れないため、その部分に血栓があると特定できます。
造影CT検査の流れは以下のとおりです。
1. 造影剤を静脈に注入します。
2. CTスキャンを行い、肺動脈の画像を撮影します。
3. 医師が画像を詳細に分析し、血栓の有無や位置、大きさを確認します。
造影CT検査は非常に精度が高く、短時間で結果が得られるため、肺血栓塞栓症の診断に広く用いられています。
・その他の検査
状況に応じて、以下のような検査も行われることがあります。
・胸部レントゲン検査:肺の状態を大まかに確認します。
・心電図検査:心臓の電気的活動を記録し、心臓への負荷や異常を調べます。
・心臓超音波検査(心エコー):心臓の構造や機能を評価し、肺高血圧症の有無を確認します。
・肺換気血流シンチグラフィー:放射性同位元素を用いて、肺の換気と血流の状態を調べます。
・下肢静脈超音波検査:下肢の深部静脈に血栓がないかを確認します。
これらの検査結果を総合的に判断し、肺血栓塞栓症の診断が確定されます。
次の章では、肺血栓塞栓症の治療方法についてご説明いたしましょう。
【参照文献】昭和学士会誌 肺血栓塞栓症
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshowaunivsoc/77/6/77_661/_pdf/-char/ja
【参考文献】”Pulmonary Embolism Symptoms and Diagnosis by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-embolism/symptoms-diagnosis
4. 治療
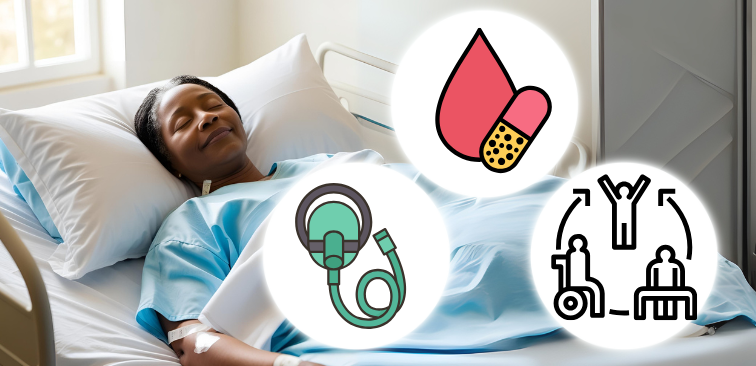
肺血栓塞栓症の治療は、患者さんの状態や血栓の大きさ、位置などによって異なります。
治療の主な目的は、血栓の進行を防ぎ、新たな血栓の形成を抑制し、肺への血流を改善することです。ここからは、主な治療方法についてご説明しましょう。
まず、診断後に行われるのが初期治療です。血栓が新たに血管に流れるのを防ぐため、ベッド上で安静にします。体内の酸素が不足している場合は酸素マスクや鼻カニューレを使って酸素を補給し、必要に応じて点滴で水分や電解質を補う輸液療法が行われます。
そして、治療の中心となるのが抗凝固療法です。
これは血液をサラサラにする薬を使って血栓の進行を防ぎ、新たな血栓を作らせない方法です。ヘパリンは注射で投与され、即効性があります。ワルファリンは経口薬で、数日かけて効果を発揮します。
最近ではアピキサバンやエドキサバン、リバーロキサバンといった直接経口抗凝固薬(DOAC)が一般的です。抗凝固療法は通常、数か月から半年以上続けます。
血栓が大きく重症の場合には、血栓を直接溶かす血栓溶解療法が行われます。
強力な血栓溶解薬を静脈注射またはカテーテルを用いて直接患部に投与し、血栓を溶かします。ただし、この治療は出血リスクが高いため慎重に行われます。
重症の場合や血栓溶解療法が適用できないケースでは、カテーテル治療や肺動脈血栓摘除術が選択されます。
カテーテル治療は、細い管を血管に挿入し、機械的に血栓を吸引・破砕します。
肺動脈血栓摘除術は、開胸手術を行い、肺動脈から直接血栓を取り除く方法です。
また、血栓が再び肺に流れ込むのを防ぐために、下大静脈フィルターが用いられることもあります。
下大静脈に金属製のフィルターを挿入し、血栓が肺に達しないようにする方法です。抗凝固療法が難しい場合や、血栓が繰り返し発生するケースで適用されます。
患者さんの状態に応じて、支持療法も重要です。
血圧を維持するために昇圧剤や心臓の負担を軽減する薬剤を使用します。
重症の呼吸不全がある場合は人工呼吸器を使用します。さらに最も重症の場合には、ECMO(体外式膜型人工肺)を使用して、体外で血液に酸素を供給します。
急性期の治療が終わった後は、リハビリテーションが重要です。
最初はベッド上での深呼吸や軽い運動から始め、徐々に座位・立位訓練を進めます。
次に短い距離から歩行を始め、徐々に距離を延ばします。最終的には着替えや入浴などの日常動作を行えるようにトレーニングを行います。リハビリを早期に始めることで、筋力低下や関節の拘縮を防ぎ、早期回復が期待できます。
長期的なフォローアップも欠かせません。
再発を防ぐために、定期的な外来受診で症状の有無、抗凝固薬の効果と副作用、血液検査や画像検査をチェックします。
生活習慣の見直しも重要で、適度な運動、水分補給、長時間の同じ姿勢を避けることが大切です。
次の章では、肺血栓塞栓症の予防法についてご説明いたします。
【参照文献】日血外会誌 『肺血栓塞栓症予防のための下大静脈フィルターの適応と功罪』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsvs/17/3/17_3_433/_pdf/-char/ja
【参考文献】”Treating and Managing Pulmonary Embolism” by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-embolism/treating-and-managing
5. 予防法

肺血栓塞栓症は、適切な予防策を講じることで発症リスクを大幅に下げることが可能です。
日常生活でできる簡単な工夫により、血栓の形成を防ぎ、健康を維持することができます。
まず重要なのは適度な運動です。定期的な運動は血液の循環を促進し、血栓の形成を防ぎます。ウォーキングや軽いジョギング、水泳やサイクリング、ストレッチや筋トレなどを日常に取り入れましょう。毎日30分程度が理想的ですが、急に負荷をかけず、無理のない範囲から始めて徐々に運動量を増やすことが大切です。
水分補給も欠かせません。
血液がドロドロになるのを防ぐため、1日に1.5〜2リットル程度の水をこまめに飲みましょう。のどが渇く前に意識して水分を摂取することがポイントです。ただし、アルコールやカフェインは脱水を招く恐れがあるため、過剰な摂取は避けるようにしましょう。
また、長時間同じ姿勢でいることもリスクを高めます。
デスクワークや長時間の移動では、1時間に1回は立ち上がってからだを動かすようにします。
飛行機に乗るときや長距離移動の際には、足首を回したり、つま先立ちをしたり、膝を曲げ伸ばししたりするなど、簡単な運動を取り入れると効果的です。可能であれば通路を歩くようにすると、下肢の血流が促進されます。
喫煙は血液を固まりやすくするため、禁煙も重要な予防策です。
タバコを吸うことで血栓ができやすくなり、肺血栓塞栓症のリスクが大幅に高まります。禁煙を成功させるためには、禁煙外来を活用したり、ご家族やご友人のサポートを受けたりすることも良い方法です。
体重管理も忘れてはいけません。
肥満は血栓リスクを高めるため、適正体重を維持することが重要です。バランスの取れた食事と定期的な運動を続け、無理なく健康なからだを維持しましょう。
手術を受ける方は、医師と相談のうえ予防策を講じる必要があります。
抗凝固薬の予防的投与や弾性ストッキングの着用、ふくらはぎを機械で圧迫して血流を促進する間欠的空気圧迫法などが効果的です。
とくに注意が必要なのは、過去に深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症の経験がある方です。また、血栓性素因のある方、がん患者の方、妊娠中や産後の女性、経口避妊薬を使用している方、高齢の方、肥満体型の方も注意することが必要となります。
このようなリスク因子を持つ方は、個別の予防策を立てることが重要です。場合によっては、予防的に抗凝固薬を服用することも検討されます。
また、定期的な健康診断も重要です。
高血圧、糖尿病、高脂血症などのリスク因子がある場合、定期的に検査を受けることで早期発見につながります。異常が見つかった場合は速やかに医師に相談し、必要な治療や生活習慣の改善を行いましょう。
このように、肺血栓塞栓症は予防が可能な疾患です。
適度な運動や水分補給、禁煙、体重管理、長時間の同じ姿勢を避けるといった日常生活での工夫が、血栓形成のリスクを大幅に減らします。
ご自分の生活習慣を見直し、必要に応じて医師と相談しながら、積極的に予防に取り組むことが健康維持への近道となるでしょう。
【参考文献】”Preventing Pulmonary Embolism” by NYU Langone Health
https://nyulangone.org/conditions/pulmonary-embolism/prevention
6. おわりに
肺血栓塞栓症は、適切な知識と予防策を持つことで多くの場合予防可能な疾患です。
主に下肢にできた血栓が肺動脈を塞ぐことで発症します。エコノミー症候群との名前でも知られていますが、飛行機への乗車以外のさまざまな場面でも注意が必要です。
突然の息切れや胸痛、咳などの症状が現れた場合は、肺血栓塞栓症の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診することが重要です。
診断には血液検査や造影CT検査が用いられます。治療法は患者さんの状態によってさまざまな方法があり、抗凝固療法や血栓溶解療法などが選択されます。
発症リスクを下げるためには、適度な運動や十分な水分摂取、長時間の同じ姿勢を避けるなどの日常的な対策が効果的です。
肥満の方や喫煙者の方、手術後の安静が必要な際には特に注意が必要です。
肺血栓塞栓症は早期発見と適切な治療で回復が可能ではありますが、予防することが最も重要だといえます。
ご自分の健康管理を意識しつつ、ご家族や周囲の方にも知識を共有し、お互いに注意を払うことが大切です。
もし症状が疑われる場合や予防法に不安がある場合は、迷わず医療機関に相談してください。
日々の小さなからだの変化に気づき、適切なケアを続けることで、肺血栓塞栓症だけでなく多くの疾患を防ぐことができます。





